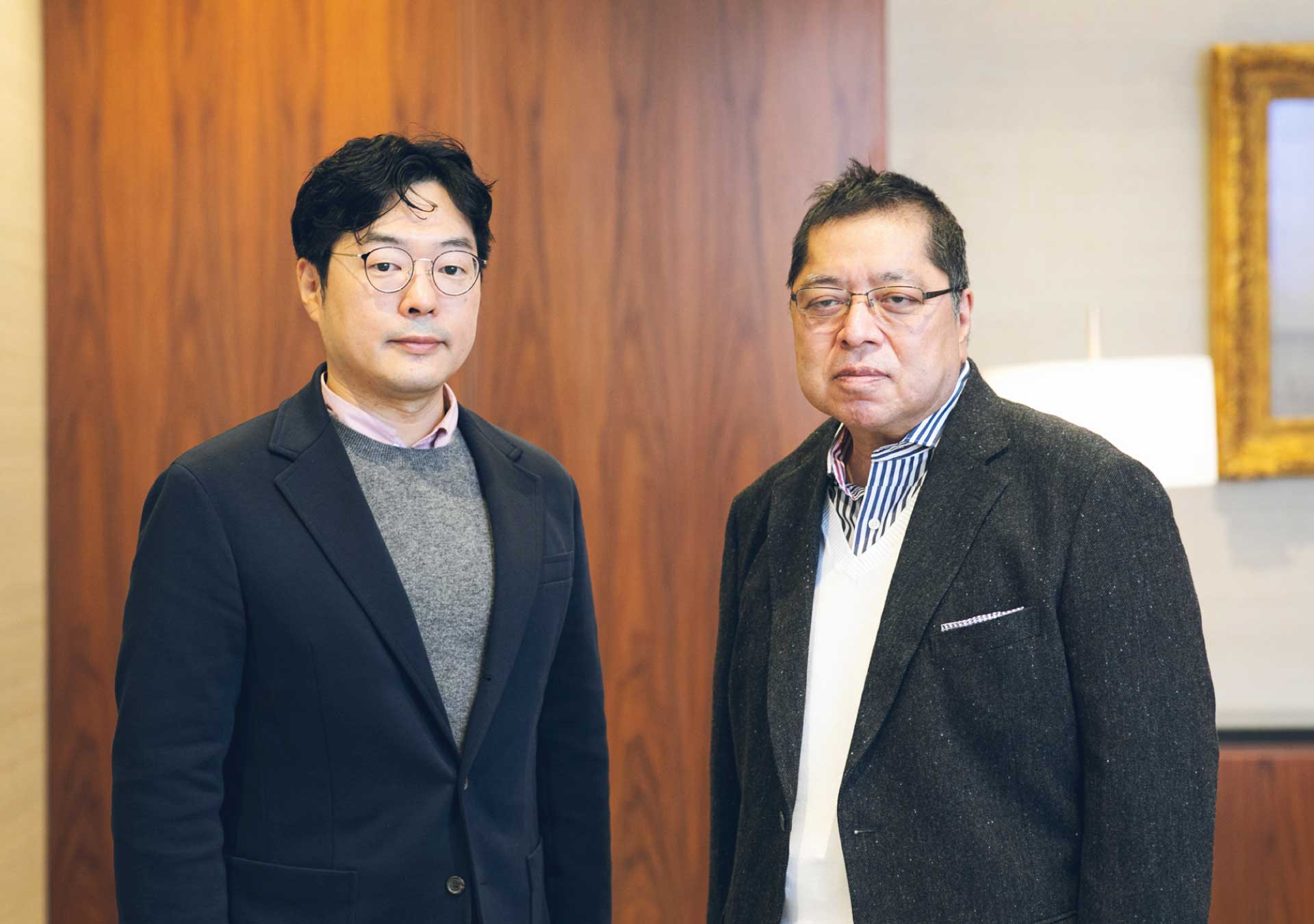「うつしだす世界」を紐解いていく。
2025年3月、三島監督は今年で30回目を迎える「あいち国際女性映画祭」のアンバサダーに就任した。2023年には『東京組曲2020』が、2024年には『一月の声に歓びを刻め』が同映画祭で上映され、監督は2年続けてキャストと共に登壇している。
「役者さんたちと舞台に上がって、お話をさせていただいたのですが、昨年、カルーセル麻紀さんが女「性」映画祭に参加されたことにも、大きな意味があったのではと思っています。『一月の声に歓びを刻め』を公開したときに思ったのは、われわれ日本人はこれまで性について本当に語り合ってこなかったし、性について未熟な国に生きているということでした。この映画祭は“女性”と付いていますが、女性、男性と一括りにできないと思いますし、そういう意味で、女性についてはもちろん、『性』についてみんなで考える、語り合えるきっかけになっていけばいいと思い、アンバサダーをお受けすることにしました」
今後はイベント出演などのPR活動で、映画祭を盛り上げていく。

言っていかなきゃいけない。
また、桜が咲く時期には、こんな催しにも参加した。
「4月に女性の映画人が集まるお花見会が東宝スタジオで開催されて、私も参加しました。100名以上の映画関係者と、その子どもたち約30名が集まったのですが、今の映画界で女性がどういうことにやりづらさを感じているのかとか、何がしんどいのかなど、みんなで赤裸々にしゃべって共有できたことはとても良かったですね」
最近は、このお花見会のような若手の女性の監督と会う機会があり、気付かされることも多いという。
「20代や30代の女性の監督たちと話していると、フルで働けない出産期間では名刺の肩書き一つとっても悩んで付けていたり、子育てから復帰した時の働き方が全然見えなかったりなど、置かれた環境でのそれぞれの悩みをあらためて知ることができました。一方で、みなさん自分らしく、自然体で映画を撮られているように感じることもありました。もちろん、私が映画界に入ったばかりの頃は、今以上に男社会で、男っぽくしなきゃとか、強く見せなきゃとか思いながら現場に入っていたんです。そうじゃないとやっていけない時代であると強烈に感じていました」

「理不尽だなと思ったり、不快だと感じても動じていないフリをしていたし、見た目も含めて、できるだけ女性を感じさせないように「頑張って」きました。でも、今はなぜそんな努力をしてきたんだろうと思うんです。ここ数年、考えていたことでもあるんですけど、今後は自分の女性性を否定することなく、あえて男性っぽくも女性っぽくもすることもなく、やっていけたらと考えています。でも、そうしていると、今度は「なんだか最近、女性っぽくなりましたね」とか、「最後のあがきですか」みたいに言ってくる人がいるんですよね。ほんとにつまらない言葉だし、ちゃんと嫌だし、不快であるということを言っていかなきゃいけないと思いました」
一連の思いを自身のFacebookに書いたところ、こんな反応があった。
「最初、そうした嫌な言葉に対して、「私は気にしてないですが」と書いたんですが、仲良くさせていただいている長野の映画館の方が「三島さんが気にされなくても、わたしはそんな言葉を三島さんにかける人たちに怒りを覚えます」と書いてくれて、ああ、「気にしてない」と書くことによって、そうした言葉を許してきたんだなとあらためて思ったんです。その方には「ありがとうございます。気にしてないは嘘かもしれません。不快だ、が正直な気持ちです。改訂しました」と返信して、文章を書き直しました。むしろ、年齢で言うと、先輩として、あなたの気持ちを理解してます、同じ側に立ちますよ、きちんと一緒に物申しますよ、と言える立場でないといけないのに、自分が自由でなくなっていることに年下の仲間から気づかせていただきました」

感謝の気持ちでいっぱい。
SNSに意見を書くことには、葛藤もある。
「言いたいことや考えている大事なことは、なるべく映画で昇華したいし、作品に込めたいというのが基本的な考え方としてあります。あまりSNSには投稿しないようにしているんですが、私が物申すことで救われる人もいらっしゃるとしたら、難しいとは感じていますが、いろんな形でやっていけたらと考えます」
この春からは、中日新聞でコラム連載もはじまった。木曜朝刊・カルチャー面のコラム「エンタ目」は、三島監督を含めた4人の筆者によるリレー形式となっており、三島監督の次のコラムは、6月5日に掲載される予定だ。
「4月10日、第一回目のテーマは「映画とごはん」。食べ方に表れる感情や生き方について書かせていただきました。映画づくりを通じて、社会、人生、ささいな楽しみをコラムで発信していければいいのかなと思っています。これまで、PHP「くらしラク~る」さん、神戸新聞さんでの「随想」と、コラムの連載をさせていただきましたが、今回は『少女』という映画で撮影させていただき、記者の方に取材いただいたご縁で、愛知でも連載できますこと、本当に楽しみで、感謝の気持ちでいっぱいです」
そんな三島監督には、コラムを書く上で影響を受けた人物が3人いる。アメリカのコラムニストのボブ・グリーン、アメリカの小説家で詩人のポール・オースター、そして、毎日新聞の元記者の深井麗雄だ。神戸新聞のコラム連載では、身の回り半径5メートル以内で起こった出来事を中心にエッセイを書いている三島監督だが、頭にはいつもこの3人の文章があると語る。
「かつてボブ・グリーンが新聞のシカゴ・トリビューンで書いていたコラムが大好きでした。彼は、誰かの身の回りで起きた出来事から書き出し、客観的情報と最後に書き手自身の独自の言葉で普遍的なコメントに持っていくという構成で、それがとても私の中でしっくりきたんです。ポール・オースターがラジオ番組で一般の方から集めたエピソードを文章にまとめた本「ナショナル・ストーリー・プロジェクト」を愛読しています。この本には、〝普通〟の人々が生きている中で体験した、ささやかだけど胸に迫る瞬間がいくつも書かれていて、もう何度も読み返しています。ポールの文章は圧倒的に素晴らしいです」
三島監督にとって、“身の回りのささいなできごと”は大事なキーワードの一つ。
「深井麗雄さんは、大学時代に毎日新聞のコラムを読んで、私もこういう文章が書きたいと、弟子(?)にしてもらったんです。深井先生からはたくさんのことを教わりましたが、特に「ニュースは自分の周りにいくらでも転がっている」という言葉が強く印象に残っています。深井先生の書くコラムは、大きなニュースを題材にすることもあれば、誰も気に留めない小さなニュースをテーマにしていることも多いんです。でも、ボブ・グリーンやポール・オースターと同じように、視野を広げていくと、それが今の時代を表現しているし、普遍的でもある。小さなニュースを拾うには「自分のアンテナをいつも張っているしかない」と、深井先生はおっしゃっていました。例えば、道端に今までにはない花が咲いていたら、誰かが植えているのかもしれないし、どこからか種が飛んできたのかもしれない。もしかしたらそこを辿ることによって、大きなドラマが見えてくるかもしれない。目を留めるかどうか、探っていくかどうか、つなげていけるかどうかだと深井先生は教えてくださいました。その後、NHKに入って、企画・ディレクターをしたNHKスペシャル「配達された幸せ」は、たった3行の記事から取材を始めて企画したのもその影響です。深井先生とボブ・グリーンとポール・オースターの文章は私の目標ですし、3人の物事の捉え方は、映画の企画を考えるときの指針にもなっています」

撮影/野呂美帆
BACKNUMBER
- vol.1
- vol.2
- vol.3
- vol.4
- vol.5
- vol.6
- vol.7
- vol.8
- vol.9
- vol.10
- vol.11
- vol.12
- vol.13
- vol.14
- vol.15
- vol.16
- vol.17
- vol.18
- vol.19
- vol.20
- vol.21
- vol.22
- vol.23
- vol.24
- vol.25
- vol.26
- vol.27
- vol.28
- vol.29
- vol.30
- vol.31
- vol.32
- vol.33
- vol.34
- vol.35
- vol.36
- vol.37
- vol.38
- vol.39
- vol.40
- vol.41
- vol.42
- vol.43
- vol.44
- vol.45
- vol.46
- vol.47
- vol.48
- vol.49
- vol.50
- vol.51
- vol.52
- vol.53
- vol.54
- vol.55
- vol.56
- vol.57
- vol.58
- vol.59
- vol.60
- vol.61
- vol.62
- vol.63
- vol.64
- vol.65