

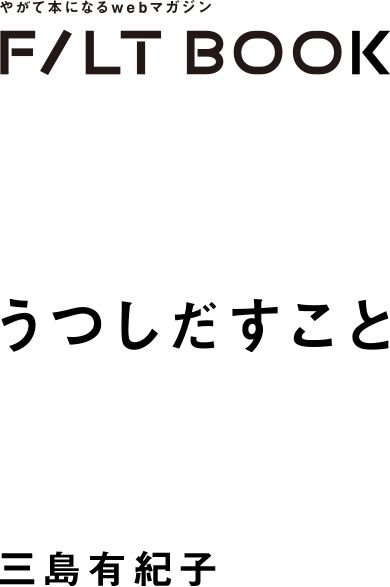
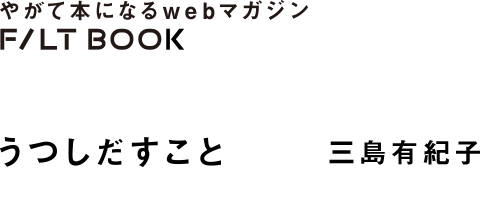
撮影/伊東隆輔
取材・文/中村千晶
スタイリング/谷崎 彩
衣装協力/シャツ、Tシャツ EDSTROM OFFICE(03-6427-5901)、
赤いデニム Levi's® made & Crafted®(リーバイス・ストラウス ジャパン株式会社 0210-099-501)
取材協力/和敬塾
書くことの意味と、楽しさと怖さ。
何かと何かをつなぐことの幸せ。
三島監督は「書く女」だ。目にした出来事、耳にした会話から着想を得て、物語を書く。
「永井愛さんの『書く女』が好きなんです。樋口一葉を主人公に彼女が愛したとされる師匠への恋心と、その想いが成就しない苦しみが描かれる。一葉が想いを抱えながら執筆し、作家として成長していく姿を描いた作品です」
戯曲の中に、一葉の恋心がある日突然消えてしまった、という瞬間が描かれている。
「『私の恋心はどこへ行ってしまったのか』と問い、『そうだわ、この中に入ったのよ』と自身の小説を手にするシーンが好きなんです。私も現実の世界では解決しない様々なことを、書くことによって消化していると感じるんです」
オリジナル脚本の『しあわせのパン』『ぶどうのなみだ』は小説としても刊行。ショートストーリーを雑誌に連載していた時期もある。
「映画は多くの人が関わるプロジェクトでありたくさんの人の才能や力が積み上がって生まれる。自分のイメージを越えたものが生まれる瞬間が何より至福の瞬間です。完全に自分の思い通りになることはない。むしろそこが面白い」
文章に書く行為は
自由になれる
瞬間でもある

「けれど、小説は自分が書けばその世界が生まれ、100%思い通りになる。ただ、すべてが思い通りになってしまう恐さもあります。筆力が届かず、歯ぎしりすることも多いですし。何でしょうね。自分の見てきたもの、感じたことを、予算や時間に制約される事なく“ただ文章に書く”行為は、私にとって自由になれる瞬間でもある。でも、撮影行為と平行して存在するから、バランスがとれている。どちらか一方でもダメですね。映画が外に向けてだとすると、書く事は外の世界と遮断して、自分を自分にしてくれるものなのだと思います」
ロケバスの中で、喫茶店で、街角で。思いついたことを書き留め、物語を紡ぐ。
「何かひとつ象徴的な出来事に出会ったり、映像を見たり、会話を聞いたりすると、そこから書き始めることが多いですね。一言のものやショートストーリー、小説、脚本。世に出るか出ないかは関係ありません。ただ、記す。ですが、脚本にまでしたものは、いつか実現させたいです」
中には映画のセリフのように深く、心に刻まれる言葉もある。
「歳の離れた友人がいるんです。私が、『NHKを辞めて映画をやりたい』と思ったときにまず相談をした方で、あのときは一晩中かけて『三島の未来を考える会』を開いてくれました。結局、その2週間後にNHKを辞めて演出部見習いとなり、電気も止められるような暮らしになったんですが、そんな中でもその人は何ヵ月かに1度、美味しいワインや食事をご馳走してくれた。敬愛する先輩であり大切な恩人でもあります。その方が最近、施設に入られたんです」
物語のセリフの
ような言葉を、
人はふっとつぶやく。

「最近は、いろんな多くのことを忘れる事が多いと聞いていました。先日、お会いしに行って私のことをもしかしたら憶えていないかな、と思ったら、『顔がシュッとしてて、いいじゃない』と笑ってくれて、ああ、憶えていてくれてると安心した。そのとき彼女が言ったんです。『私ね、ちょっと頭が人間じゃなくなってるみたい』」
この人は忘れていくことを、その刹那を認識しているんだ――その言葉がずしりと響いた。
「思わず書き留めました。思いがけない言葉を、人はふっとつぶやくんですよね」
これまで多くの言葉をもらって生きてきた。最近は自身が、言葉を渡す側にもなっている。
「先日、スタッフの女の子が『映画は大好きだけど、この道に進み続けるには、あまりにも捨てるものが多すぎる』と、涙ながらに仕事を離れたいと言ったんです。よく考えて決心したのならそれでいいし、またやりたくなったら戻ってくればいい。ただ、ひとつだけ言えるのは何も捨てなくていい仕事は、たぶんないよ、と。何かを選ぶ事は何かを捨てる事だと思うよ、と伝えました」
全てのものは手に入らない。それが人生。
「最近、人間と動物の違いってなんだろう? と考えて、それは『死者との対話』ではないかと思ったんです。亡くなった人を弔い、想い、その人と対話することを望む。それは人間だけがする行為なのじゃないかと」
それはつまるところ、自分自身との対話なのかもしれない。そんなことを考えるうちに「自分が死ぬ前にやるべきことは何なのか」と思い始めた。
「何かと何かをつないでいけたら幸せだなと思っているんです。映画の中で、こんな人とこんな人を出会わせたい、映画の外で、この人とこの人、この人とこの映画を巡り合わせたい。この景色をこんな人に見せてあげたい。その考えが、いま取り掛かっている作品につながっています」

新作は大人のラブストーリーだ。ある人と出会ったことによって主人公の何が変わるのか。それを描こうとしている。
「これまでの映画は常に、観た人の誰か一人にでも『世の中、そんなに捨てたもんじゃない』『それでも生きていく』と思ってもらえたら、という気持ちで作ってきました。ハッピーエンドの物語とは限らないし、どん底にいる人や悲惨な話かもしれない。それでも観た人に何かしらのエネルギーを受け取ってもらえる、それが映画だと思っている。最近は生きていこうと思えるのは『この人と出会えたから』『これとつながれたから』の連続ではないかとより強く思い始めた。今回の作品に着手し始めてからの変化かもしれませんね」
次なる新作は、何を我々につないでくれるのだろう。

三島有紀子 みしまゆきこ 大阪市出身。18 歳から自主映画を監督・脚本。大学卒業後 NHK 入局。数々のドキュメンタリーを手掛けたのち、映画を作りたいと独立。『幼な子われらに生まれ』(’16年)では、第41回モントリオール映画祭審査員特別グランプリ、第42回報知映画賞監督賞などを受賞。他の代表作に『しあわせのパン』『繕い裁つ人』『少女』などがある。上梓した小説には『しあわせのパン』(ポプラ社)、『ぶどうのなみだ』(PARCO出版)。2018年にはエル ベストディレクター賞を受賞。
撮影/伊東隆輔
取材・文/中村千晶
スタイリング/谷崎 彩
衣装協力/シャツ、Tシャツ EDSTROM OFFICE(03-6427-5901)、
赤いデニム Levi's® made & Crafted®(リーバイス・ストラウス ジャパン株式会社 0210-099-501)
取材協力/和敬塾