
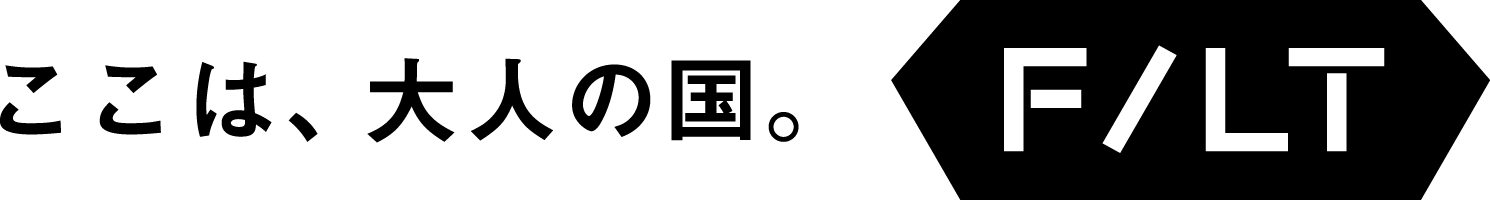


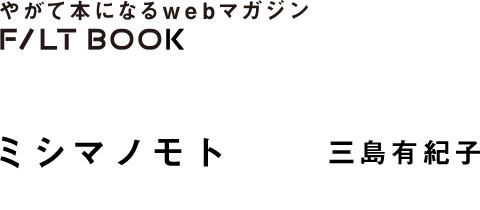
撮影/伊東隆輔
歌詞のたったひと言で世界が変わる。
それを最後の歌で流したかった。
「エンドロールが終わって、暗い空間が明るくなるまで。そこまで含めて私は映画だと思うんです」
映画監督・三島有紀子はそう語る。だからなのだろう、三島の作る作品の音楽はどれも映画を観終わった後も体のどこかに余韻を残して、映画自体を深く私たちに刻んでくる。
たとえば先日公開された『繕い裁つ人』のエンディングテーマは財津和夫が作詞・作曲した「切手のないおくりもの」を平井堅が歌ったもの。そして『しあわせのパン』では「ひとつだけ」という矢野顕子の歌を忌野清志郎と共に彼女が歌ったものが使われている。いずれの歌もまるで作品のために作られたように響き、作品の最後に染み渡る。
「映画で、自分が使いたいなと願った曲をかけるのはなかなか大変なことですが、いずれの作品も作る際に思い描いていた歌を使用することができました。『しあわせのパン』は作品のテーマとして“気持ちをシェアする“というものがあったんです。なので「ひとつだけ」以外は考えられませんでした」

最初に聴いたのは
ルイ・アームストロング
小学生でしびれた。
この「ひとつだけ」。実は矢野顕子のオリジナルソングだが、エンディングに流れるのは忌野清志郎と共に歌っているものをあえて選んだという。
「歌詞の中で“心の白い扉”という部分を”心の黒い扉“と変えて歌っているんです。相手の闇を知っていて、それをほどいてあげることが自分の願いである、そういう深さというか…このひと言で、今まで聞いていた矢野さんの歌の時に感じていた世界より、さらに大きく広がった。そしてこの受け入れる感じが映画の最後に流れてほしいと思ったんです」
たったひと言。歌詞のたったひと言かもしれない。でもこのこだわりがあるからこそ、三島監督の作品は頭にも体にも残るのだろう。それにしてもこの音楽へのこだわりはどこから生まれたのか。
「最初に手にした音楽は、兄貴からもらったルイ・アームストロングの『What a Wonderful World』です。10歳歳の離れた兄貴から“これめっちゃええから聴いてみ“っていわれて。小学生のくせにこの音に“しびれるわぁ”とか言ってました。でも初めて買ったのは山口百恵さんの『愛の嵐』。でもやっぱり最初に聴いたルイ・アームストロングの影響は大きかったです」
どんな音楽を好きになるか。
それはだれに聴いても、やはり多感な時期に何を聴いていたかが大きく影響すると話しているのをよく聞く。とはいえ三島監督の中学時代といえば、監督もレコードを購入した山口百恵をはじめ、松田聖子、中森明菜や多くの男性アイドルたちが今以上にテレビやラジオから歌を聞かせていたころ。中学生女子であればそれなりにアイドルへ心動くこともあっただろうけれど、有紀子少女はバスケ部で活躍をしながら、同時に「アメリカ民謡クラブ」の扉をノックしたという。

ジャニス・ジョプリン。
彼女の音楽も生きざまも
すべてに影響を受けた。
「アームストロングから、黒人霊歌とかソウルが好きになっていたのですが、そのあたりのレコードを収集している先生が、そのアメリカ民謡クラブを運営していてアームストロングやナット・キング・コール、アレサ・フランクリンとか聴くっていう話をしていて…率先して入部の手を上げました。実は小学生の頃アメリカの奴隷制度を描いた「ルーツ」というドラマが放映されていて、そこで黒人霊歌などができた背景を知ったのもあって、クラブ活動は楽しんでいました。みんなで歌の内容と背景を理解して、最後に合唱するみたいな。歌謡喫茶みたいですよね、今考えてみると(笑)」
歌ができるのには物語がある。歌にして伝えたいしあわせや、歌にして忘れたい悲しみ。言ってみれば歌に込められた「魂」というものだろうか。中学時代の監督は歌のルーツを学び、それを歌うことを喜びとしていたが、のちにその「歌の魂」に触れることになったと話す。
「本当にたくさんの音楽を聞いてきました。でも、ジャニス・ジョプリンの『move over』を街中で聴いたときの衝撃は忘れられません。雷に打たれました。魂の声とはよくいわれますが、まさにそうだと思います。表現者として彼女から受けた影響は少なくありません。それこそ片っ端からジャニスの音楽を聴き、伝記を読み漁りました」
シャイだけれど溢れる思いを生々しく謳いあげるジャニス。目の前で話す三島監督にはその面影を感じるような気がする。でも、きっとこうやって書いたら、監督は絶対に謙遜してこの部分を削ってほしいというと思う。でもあえて書かせてもらう。やっぱり三島監督はジャニスっぽいところがある。監督は自らのことを語ることも、例えばこの連載で写真を撮影されるときも、どこか所在無げなのである。でも、一度映画に話が及ぶと言葉があふれてくる。そして、その言葉の端々からは物を作る覚悟というものがひしひしと感じられるのだ。
「音楽もそうだけれど、私が心動かされるのは“それでも人は生きていく”というその姿。ボロボロで、もがいて、あがいてもそれでも生きていく人の美しさを映画の中でも描いていきたいんです」
最新作の短編映画『オヤジファイト』では甲斐バンドの「らせん階段」という歌をテーマに、マキタスポーツ演じる主人公が別れた妻との復縁の為に無様になりながらも、よろめきながら生きていく姿が描かれる。
”人生なんてそんな悪い旅じゃないはず“
流れてくる甲斐バンドの音楽と映像に、かすかな希望の光が心に湧いてくる。それはきっと監督がこれまで聴いてきた音楽たちのエッセンスが、作品の中に込められてるからかもしれない。代わり映えのない日常も、うだつの上がらない毎日でも「What a Wonderful World」なのだから、と。

三島有紀子 みしま・ゆきこ 大阪府出身。18歳から自主映画を監督・脚本。大学卒業後NHKに入局。数々のドキュメンタリーを手がけたのち、映画監督になる夢を忘れられず独立。撮影所の助監督などの仕事をしながら脚本やテレビの演出を手掛け、‘12年『しあわせのパン』がヒット。最新作は甲斐バンド短編映画作品集「破れたハートを売り物に」に収録された『オヤジファイト』。
撮影/伊東隆輔