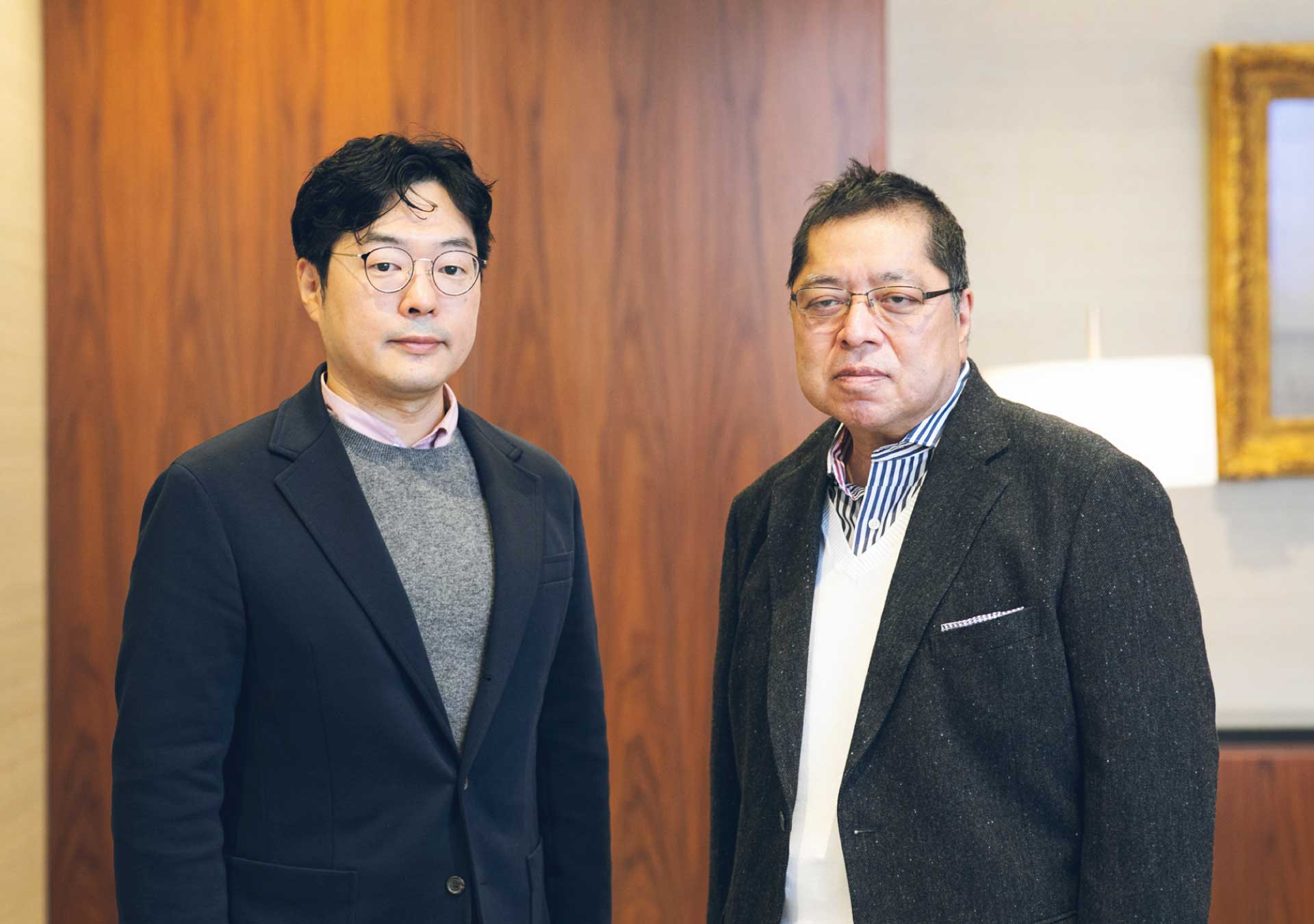「うつしだす世界」を紐解いていく。
『一月の声に歓びを刻め』は、海の深い青と自然の濃い緑が溶け込む八丈島から撮影がはじまった。映画が公開されて約1年。八丈島篇で牛飼いの男を演じた哀川翔と、三島監督は再び共に作品を作ることになる。現在、三島監督が企画・撮影を手掛けたJTマナー広告/「私はマナー人」哀川翔篇が、YouTubeのJT公式チャンネルで公開中だ。
「翔さんともう一度ご一緒できたのは、とてもうれしかったですねぇ。次は翔さんのどういった部分を撮ろうかと、新たな探求がはじまった心持ちでした。撮影をするにあたって大切にしたのは、翔さん自身の言葉です。まず、翔さんの名言集『翔、曰く』を読み返して、いくつもの哲学をきちんと言語化し、それを行動に移している強さを改めて感じました。だから、観てくださる皆さまに、翔さんの“映画俳優として生きて来られた人生”をお伝えしつつ、“好きな自分をやり続ける”、この言葉をキーワードに作ろうと考えました」

こんなに素敵な大人になるんだ。
動画は2人の哀川翔が電話ボックスから電話をかけ、「俺は全部一生懸命やるよ」「嘘はつかない」と話すところからはじまる。
「大人になると物事をうまく回すために嘘をつくこともあるし、それが仕事のできる人という評価になることも多いと思うんです。でも、翔さんには、いつも嘘がない。嘘をつかずに周りの人をハッピーにして、元気を与えています。嘘はつかないとか、一生懸命やるとか、信念に従って生きていると、こんなに素敵な大人になるんだと思いました」
2人の服装はスーツとツナギ。三島監督はそれぞれ異なる背景を設定した。
「ツナギの翔さんは、港湾や工事現場で働いているイメージです。電話の向こうには小さい子どもがいて、その子のためになけなしの十年玉を投じ、自分の大事にしている生き方を語りかけています。彼自身はその子と一緒に暮らせない事情があって、どういう関係かはわからないけど、子どもとその母親に仕送りもしている。学校で先生に怒られたとか、友達にいじめられたとか、その子の話を聞いているうちに、最後に言ってあげられることはなんだろうと考えて、生きていくための基本を優しく教えてあげているところです」

一方、スーツ姿の哀川翔が電話をする相手は、弟分のような男。『一月の声に歓びを刻め』における誠(哀川翔)と龍(原田龍二)の関係性に近いのかもしれない。
「罪を犯した弟分が逃亡していて、心配した兄貴分が、足がつかないように公衆電話から電話をかけているというイメージです。そこで翔さんは「押し付けるのも押し付けられるのも嫌だ」と言います。結局、犯罪って何かを押し付けようとするから起きるように思ったりもします。例えば痴情のもつれによる殺人も「俺は好きなんだ」という押し付けがきっかけですよね。電話の相手が逃亡中の犯罪者というのは、たまたま私がそういうふうに設定しているだけですけど、つまり押し付けるのもダメだし、押し付けられるのもダメだよねということを翔さんに言ってもらえたら、届く人がたくさんいるんじゃないかと思って、ああいう演出にしました」
象徴的なのは、電話ボックスの後ろに広がる風景だ。2人が電話しているのは、一見それぞれ異なる場所のようだが、最後に同じ海辺だったことが明かされる。
「スーツ姿の翔さんの場面では何本もの電柱が並んでいて、ツナギ姿の翔さんの場面では空が映っています。最後の引きの場面では水平線が見える同じ海辺にいたことがわかるんですが、どんな人でも“好きな自分をやり続ける”ための哲学を持っていて、それを大切な人に伝えていくことが大事だという想いを最後のカメラに向かってくるカットに込めました。作品として観てほしいというのはもちろんありますけど、それよりも翔さんの考え方が届いてくれるといいなと思っています」

裏を読ませない撮り方をした。
普段の映画づくりと大きく異なることもあった。それは“言葉”の扱い。
「映画を撮るときは、セリフは大事ですが、どちらかというと言葉をそんなに信用していないんです。例えば、「嫌い」という言葉が「好き」を表していることもあるし、その逆もありますよね。言葉どおりに受け取らないのが映画のお芝居ですし、もっと言えば20%が「好き」で80%は「嫌い」みたいな感情のグラデーションになることがほとんどなのではないかなと捉えています。心の奥に見えてくる本当の想いをカメラの撮り方だったり、役者さんの表情だったり、小道具だったりで演出するわけですけど、でも今回は、翔さんの言葉を100%届けるという思いで撮ったので、裏がないというか、裏を読ませない撮り方をしました。言葉がそのままの意味でストレートに届くように撮るというのは、いつもの映画ではすごく少ない気がして、それはそれで興味深かったのです」
電話ボックスは、100%の言葉を届けるためには最適なアイテムだった。
「言葉だけを伝えようと思ったら、翔さんがどこかに座って携帯電話でしゃべってもらってもいいと思うんです。でも、電話ボックスの中から電話をしてもらうことで、電話の相手に集中してしゃべっているということを視覚化できるのではないかなと思いました」
30秒の動画ながら、一つの映画作品になった。
「それは、スタッフや翔さんの力だと思います。スタッフはみんな映画のスタッフですし、翔さんも映画俳優なので。私が書いたつたない脚本とアイデア(一人二役、電話ボックス)をみんなで作り上げてもらえた。片岡礼子さんにも同様のことを言っていただいて、映画監督として、翔さんが生きて来られた人生を感じていただきながら、翔さんの言葉を届けるという役割は果たせたのかな」
届けるという意味では、三島監督はここ数年、精力的に役者の演技ワークショップで若手育成を続けている。緊張した役者たちが体をほぐしながら自分のことを語るワークを始めると、段々と柔らかくなり、顔つきが変わって、心も体もオープンになり、やがて笑いが絶えなくなる。
「現場でも大事にしていることは、まず安心感。どんなことをやってみても、おもしろがって受け止めてくれる演出家がいて、相手役がいると思えること。そのために、相手に必ず集中する、反応することで、互いに安心感を得られることを体で覚えてもらうワークから始めます。結局どんな感情が人間と人間の間に流れていくのか、それがどう肉体や表情に表れるのかを撮っていきたいからなんでしょうね。それはきっと役者さんが「感じる」ということ、そして「反応」すること、その繰り返しだと思っているから、そこに向かっていけるためのワークをこれからも届けていきたいと思っています」

撮影/野呂美帆
BACKNUMBER
- vol.1
- vol.2
- vol.3
- vol.4
- vol.5
- vol.6
- vol.7
- vol.8
- vol.9
- vol.10
- vol.11
- vol.12
- vol.13
- vol.14
- vol.15
- vol.16
- vol.17
- vol.18
- vol.19
- vol.20
- vol.21
- vol.22
- vol.23
- vol.24
- vol.25
- vol.26
- vol.27
- vol.28
- vol.29
- vol.30
- vol.31
- vol.32
- vol.33
- vol.34
- vol.35
- vol.36
- vol.37
- vol.38
- vol.39
- vol.40
- vol.41
- vol.42
- vol.43
- vol.44
- vol.45
- vol.46
- vol.47
- vol.48
- vol.49
- vol.50
- vol.51
- vol.52
- vol.53
- vol.54
- vol.55
- vol.56
- vol.57
- vol.58
- vol.59
- vol.60
- vol.61
- vol.62
- vol.63
- vol.64
- vol.65