


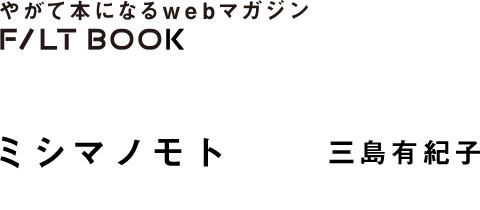
撮影/伊東隆輔
映画の空気や光をわかってもらうため、
一枚の絵を差し出す
「映画を作るときに、“こんなイメージの作品にしたい”というそのイメージを伝える手立てとして絵を使うことがよくあるんです。『ぶどうのなみだ』の時はアンドリュー・ワイエスの絵をスタッフや出演者の方に見て頂いたり、『繕い裁つ人』の時は、主演の中谷さんにもやはり同じように絵を見てもらったんです。ヴィルヘルム・ハンマースホイという作家の19世紀末の作家の絵なのですが、そのポストカードをお渡ししました。絵というビジュアルで共有すると、私が作品の中で描きたい光や空気感、色みたいなものも含めて作品の方向性をわかってもらいやすいんです」
そう語る三島監督。芸術家の名前も次々と飛び出してくるので、自身も絵を描いてきたのだろうと尋ねると「そんなことないですよ。絵を描くのは好きなんですけど、下手です(笑)。でも小学校の美術の先生が“三島さんの絵はいいね”と一度だけ褒めてくれて。上手くはないけれど、楽しそうに取り組む姿を見て、それを含めて褒めて伸ばしてもらった気がします」

映画は時間の共有
絵は想像する時間をくれるきっかけ

時間があれば美術館を訪ねたり、画集を買い求めているという監督。人物や風景を切り取るという行為として考えれば映画も絵画も同じようなアートワークと思えるのだが、映画と絵の大きな違いはあるのだろうか。
「映画って時間の共有だと思うんです。その映画を見ている時は同じ想いを映画と過ごしている。でも絵は思いを巡らす時間のはじまりをくれるものなのかな。その絵を見たときに“絵の中に描かれた人物はなぜここにいるのだろう“”何を感じているんだろう“そんな想像を巡らす時間のスタートをくれるのが絵じゃないかな。映画はみんなで作る総合芸術で、絵は一人の作業という違いも大きいですね」
どうしても本物を見たいとなったら、その一枚を見に遠くまででも出かけていくという監督。
「ジョージ・トゥッカーの「地下鉄」という絵があって、ニューヨークの地下鉄の改札を出てくる人たちを描いているのですが、その誰も視線が合わなくて…。都会の中の寂しさとか冷たさとかそういうものが一枚に描かれていて。どうしてもそれが見たくて、一人、ニューヨークに旅立ったこともあります」
多くの作品を見ている三島監督。その中でも好きな作家を尋ねると「マグリット」と。真っ黒なスーツに真っ黒の帽子をかぶった男性が空から雨のように降り注いでいたり、巨大な石が空に浮かんでいたりと、まさにシュルレアリズムを代表する作品を描き出してきたルネ・マグリット。心の機微を丁寧に描く三島監督の作品とは印象がかなり違う。
「そうですね。でも、私が心を動かされるのは“この人にしかない世界を描いている”なんです。あの水色と黒のコントラストも、顔の見えない男性も、彼にしか描けない世界ですし、黒色の魅力を教えてくれたのもマグリットでした」
リアルとファンタジーの
その間を描いているものが好き

独特の世界観といえば監督は河鍋暁斎も好きだという。幕末から明治にかけて活躍をした日本の画家で多くの作品を残した浮世絵師であり、日本画家だ。
「彼の作品には鬼や妖怪、死後の世界…それこそしゃれこうべのようなものをたくさん描いているのですが、そのどれも生き生きとしているんです。死んでいる人を描いているのに(笑)。風刺が効いていて、どこかクスッと笑ってしまうような洒落っ気もあるし、独特の色使いや、筆の力強さ、どれをとっても昔描かれた絵とは思えない生命力にあふれていて。暁斎の作品も埼玉に美術館があると聞いて、一人訪ねました」
作品に対する思い入れもそうだが、何よりも“その絵を見たい”と思った瞬間に一人でも日本全国、そして世界まで飛び出すその監督の行動力も目を見張るものがある。
「実は絵だけじゃないんです。どうしても観たい俳優が出演している芝居を見るためだけにロンドンのウエストエンドに行きました(笑)でもその後ジリ貧です」
そこまで三島監督を突き動かすものとは一体なんなのだろう。
「リアルとファンタジーの隙間みたいなものを描いた作品が好きなのかもしれません。写真ももちろん好きですが、見たものをそのままこちらに手渡されるより、見た瞬間に違う世界をふと想像させてくれるような。そういうものを追ってしまうところがあります」
目の前に広がる自分の毎日は“リアル”でいっぱいだ。やらなくちゃいけないこと、守らなくちゃいけないこと…。そんなことばかりでは疲弊してしまうからこそ、私たちは映画や本、絵画などで違う世界を訪ねるのかもしれない。そしてそれは三島監督も同じだという。
「私は映像を作るためにどこまでも考えるのが好きなんです。それこそ時間を問わず考えているバカなんで、仕事の糧として絵を見ることはありますが、本当は何よりも自分の心の栄養のために見ているんでしょう」
そんな三島監督が手掛ける作品が、私たちにとっては心の栄養となるのだが、監督は自身の映画を通じて見せたいものという一貫したテーマはあるのだろうか。
「私が映画で撮りたいものは“渇望している人”の姿かもしれません。何かを必死で求めている、無理かもしれないとわかっても手を伸ばしてしまう、そんな人を描いていきたいです。渇望って切ない。望んでも望んでも手に入らない、けど望む姿ってとても色気があると思います」

「そういう人物像に惹かれるのは、やっぱり人間として何か切実さが漂うからだと思います。そうやって渇望して、その人が変化することを映像にしたい。変化するって、生きることだと思う。誰しも生まれたそのままでいることはできなくて、何かに手を伸ばしながらここまできたんだと思います。この変化が生まれる瞬間を映像に残したい」
長い時間話し、少し落ち着くために目の前のコーヒーを手に横を向いた。そんな姿をふと見た時、少し監督の目に涙が滲んでいたような気がしたのは気のせいだろうか。いや、気のせいではないと思う。だって、三島監督自身が「渇望している人」なのだから。監督の目の涙はきっと監督の渇望する思いが、色気を漂わせて、そう見えたのかもしれない。

三島有紀子 みしま・ゆきこ 大阪市出身 18歳から自主映画を監督・脚本。大学卒業後NHK入局。数々のドキュメンタリーを手掛けたのち、映画監督になる夢を忘れられず独立。近作は『繕い裁つ人』『オヤジファイト』などがある。
撮影/伊東隆輔