


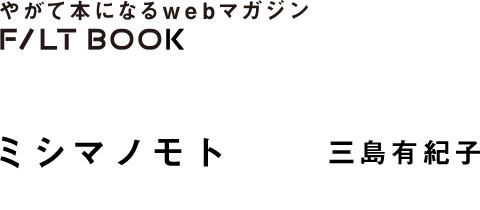
撮影/伊東隆輔
廃墟に興味がある。
人々の営みを想像するのが好きなんです。
「かつては栄えていた街が、今はこういう姿をしているという“変化”に興味があるのかもしれません。当時の生活はどんなだったのだろう。見られるものなら見てみたいです。アパートの向かいの窓越しにしゃべっていたり、高級デパートで奥様たちが買い物していたり。狭い世界の中に、すべてが凝縮されていた。炭鉱の島なので、命をかけて地の底に向かう人たちの気持ちを想像したりと…。なんだか当時の人たちの声が聞こえてくる気がするんです」
三島監督が兼ねてから訪れたかったという長崎県長崎市の端島。沖合約19kmに位置する「軍艦島」と呼ばれるこの島は昭和49年の閉山まで、世界最大の人口密度を誇っていた。
「もともと廃墟には興味があって。“消えていくその前”という魅力もありますが、こんな人が暮らしてこんな会話をしてたんじゃないかって、人々の営みを想像するのが好きなんです」
そして、三島監督は廃墟の原体験ともいえる、小学校4年生のある日の冒険について話してくれた。
見たことのない
世界を体験した
ある日の冒険。

「実家の近くに巨大な病院の廃墟があったんです。戦前からある大学の医学部の病院で、そこが子どもたちの間で謎に包まれた秘密の場所みたいになっていた。ある日、小学校6年生くらいの男の先輩がそこに『行く!』って言い出して、『じゃあ私も』って、一緒に行くことにしたんです。全部で10人くらい、子どもたちだけで夜に懐中電灯を持って。注射器とか薬品の瓶とかがあちこちに転がっている中、手術室や診察室を回って、地下に降りたら、一室が霊安室で。そこの扉をバッて開けたら、中から多数の目がギロッてこっちを向いたんです」
まるで怪談噺のような展開だが、監督は「いやいや、そういう話じゃないんです」と笑う。「私たちが『うわー!!』って声を出したら、中からコウモリが一斉に飛び出して、頭上をかすめたんです。まるでインディージョーンズ。そのときのびっくりしたことといったらなかった。腰を抜かしそうになりました(笑)」
今なお同窓会などで語り継がれる伝説になっているという、ある日の冒険譚。廃墟自体は今から10年ほど前に取り壊されてしまったが、その強烈な体験は今も監督の中に残っている。
「今考えるとよく無事だったなって。棟から棟へ行くときに、いろんなものが割れていて下の廊下が通れないから、その辺の板を窓と窓に渡して通ったりしました。今考えたら怖ろしいですよね。古い病院だったので、壁に銃弾の跡があったし、空襲で爆撃された跡も残っていた。戦争をなまなましく感じたというか。ここにいた人の上に焼夷弾が落ちてきたというような話をしながら、ひたすら真っ暗な中、懐中電灯の明かりだけを頼りに進むという。見たことのない世界が次々と目の前に現れる感じは衝撃でした。本当に面白かったんです」
人が捨てた思い出のカケラを
拾い集めている。

「廃墟は人が生きてきた証でもあるので、インスピレーションが湧いてしまいます。例えば、子どもの絵が壁に飾ってあったり、母子手帳が落ちていたり、カレンダーの日にちに○がしてあったり、そういうところから、どんな毎日を生きていたのかって想像が広がってしまう。もちろんそれが本当かどうかは分かりません。確証はないですから。でも、何かを突破口に、そういうことを考えている時間というのが、私にとっては豊かな時間なのかもしれません」
見ること、聞くこと、感じること、映画監督の三島有紀子にとって、そのすべてが作品作りのヒントになる。
「人と接するときも、『この人はどういう人なんだろう?』『なんでこんなことを言うんだろう?』って無意識に観察してしまいます。ある意味、人間の行動ファイルの一つや、キャラクターの一人として見ているところがある。でもそれに傷つく人もいるので、今は一歩引いて、自分を含めて客観的に見るようにしています。『私、このネタを使えると思ってしまっているな』というふうに」
三島監督の映画『少女』(今秋公開)の中で女子高生が男に土下座をさせるシーンがある。
「これは、私の大学時代の友達から、女子校時代に痴漢してきたサラリーマンを土下座させたというエピソードを聞いたことがあって。要は屈辱ということには、社会的に自分より上の者や、もしくは自分を見下している者に、土下座させるという方法が、ひとつあるんだなって。経済的に独立もしていない女子高生にサラリーマンが土下座させられると言うのはかなりの屈辱だなと。聞いたときは特に何も思っていないんですが、私の中にしまわれていたんです」
「何かを作るときに、『そういえばああいう話があったな』ということが無数にある。つまり、きっかけなんですかね。聞いたものをそのまま使うことはありません。この間も、録音部の重鎮と言われる方から、友達の葬式にみんなで花火を打ち上げたという話を聞いて、その設定だけをもとに、ショートストーリーを書いたんです。ある人が死んだ友人のために、冬に花火を打ち上げようと、縁(ゆかり)の人たちにお金をもらいに行く。それぞれの話を聞いていくうちに、友人の人生が浮かび上がって来る。実は主人公と友人は、生前、『死んだら遺灰をつめて大玉の花火をあげてくれよ』と約束を交わしていた…という物語。ヒントにしたのは、死んだ人のために花火を上げるという1点なんですけど、それだけでも話が広がっていく」

「そのエピソードを話してくれた録音部の重鎮は笑ってましたけど。みんなが私に話してくれることって、すべて過去のことですけど、でも、そこから閃く何かがある。その閃き、インスピレーションがものを作るきっかけになる。それはエピソードに限らず、一つの絵だったり、廃墟だったりもする。誰かが捨てていったもの。私は、そのカケラを拾い集めているのかもしれないですね。そのカケラが自分の中を通過して、消化して、新しい何かを生み出すという作業をしているのかなって」
人が口にする思い出の話、もう使われなくなった建造物、そこに取り残された品々。これまで三島監督が触れてきたそのすべては、確かに監督の中にストックされ、そして、作品として新しく生まれ変わるときを待っているのかもしれない。

三島有紀子 みしま・ゆきこ 大阪市出身 18歳から自主映画を監督・脚本。大学卒業後NHK入局。数々のドキュメンタリーを手掛けたのち、映画を作りたいと独立。近作に『繕い裁つ人』など。10月8日、死に囚われた女子高生達の、いびつな青春を描いた『少女』(原作・湊かなえ)が公開予定。
撮影/伊東隆輔