

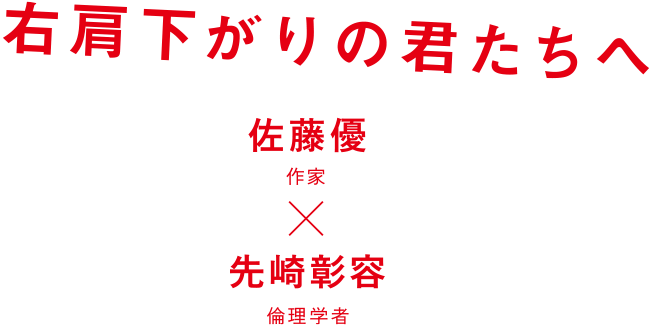
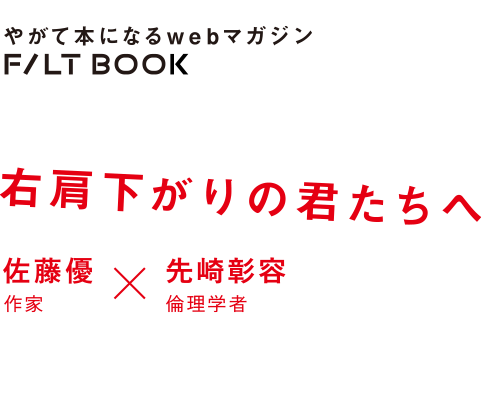

構成/藤崎美穂
撮影/伊東隆輔
撮影協力/PROPS NOW TOKYO
ナショナリズムについて考えること
ポスト・ポスト・モダニズムの論客が
現れて来たと感じました ―― 佐藤
佐藤 今回のテーマである「ナショナリズム」は、よく使われる言葉でありながらその定義が曖昧なものでもあります。先崎さんは『ナショナリズムの復権』という本を書かれていますが、そもそもナショナリズムへの関心を持たれたのは、何がきっかけだったんでしょうか。
先崎 文学部出身の私がナショナリズムに興味をもったきっかけは二つあり、まずは和辻哲郎を勉強したことです。彼は、文化ナショナリズムについて考えた人ですね。倫理学者であり、日本文化論者でもある。
佐藤 先崎さんも、大学では倫理学を専攻されていますね。
先崎 はい。和辻の倫理学は、個人の関係から国家への流れを追っていく学問です。ドイツ哲学や現象学などの影響を受けた人ですね。
佐藤 その文脈だと廣松渉も面白いですよね。廣松渉の『存在と意味』の第2巻の最後の正義論は、和辻倫理学の影響を受けている。
先崎 廣松渉が急逝直前の最後のゼミで使ったテキストも和辻の『倫理学』でした。『倫理学』は面白い本で、よくヘーゲルの影響を指摘されるのですが、実は江戸時代の伊藤仁斎の影響もかなり強いんです。そして江戸時代の日本倫理思想史で外せないのが、本居宣長。そして宣長を読むうえでの「軸」を作った丸山眞男も集中して読み込むことになり、日本政治思想史やナショナリズム論へと自然に導かれて行きました。
佐藤 丸山の古層論についてはどう思います?
先崎 丸山の論文「歴史意識の『古層』」が発表されたのが、1972年。安保や全共闘など、「政治の季節」が終わった時期であり、丸山の敗北宣言論文と言われたこともあったようです。なぜなら、一貫して近代的な人間像を追い求め、日本人へのメッセージを発してきた丸山本人が、日本人は「永遠の今」つまり現状を常に肯定しなんでも受け入れてしまうことを特徴とする、と言ったからです。江戸期の本居宣長どころではない、『古事記』の昔から、日本人の精神には同じ傾向があるのだ、それが現状肯定だというメッセージをこの論文は、多分に含んでいたのです。
佐藤 むしろ原点回帰であると。
先崎 ただ僕自身の興味は、狭義の「政治思想」としてのナショナリズムよりも、どちらかと言えばロマン主義にありました。ドイツ・ロマン主義、その影響下に文学運動をした、保田與重郎や伊東静雄などの詩人です。古都の風景を美しくも妖しい文体に載せて、日本を取り戻そうとしたロマン主義運動に当初、惹かれたんですね。2013年に『ナショナリズムの復権』を書いたのも、この郷土愛とナショナリズムとの関係を、どううまく接合するかを意識して書いている面があります。
佐藤 この本を読んで私は本格的なポスト・ポスト・モダニズムの論客が現れて来たと感じたんですよ。私は1960年生まれなので、本来であればポスト・モダンに影響を受けている世代なんですが、1986年に日本を出て1994年に戻ってきたので、すっぽりと日本のバブル経済と、ポスト・モダニズムの流行が抜けているんです。
先崎 そうですね、僕も図らずもそうなっている部分があります。学部生時代には、ポスト・モダニズムの入門書みたいなものを周囲が乱読し私自身も貪り読んだわけですが、その中にある相対主義的な匂いは19歳くらいでもよく分かりました。これだけ刺激のないのっぺりとした社会において、さらに価値の相対化を提唱されたら、いったい自分はどうしたらいいんだろうと、身体的な嫌悪感を覚えたんです。
佐藤 ソ連時代のスターリニズムのように非常にかっちりした公認のイデオロギーがあるところでは、知識人は相対主義的になって当然です。
被災した人たちの心情を、
流浪を肯定する思想でカバーできるのか ―― 先崎
佐藤 そうでなければ、あんなバカバカしい体制のなかで知的営為などできない。しかしそこまで強固なイデオロギーがなくなったらどうなるか。マルクス主義的な図式でいうと、資本の運動に吸収されるだけです。ドゥルーズやデリダが出てきたとき、一番熱心に読んでいたのは大手広告代理店の連中だって聞きました。分かりやすいよね。小さな差異を作り出すことで、金にしていく。
先崎 資本主義の競争社会は、「新しい発想だ」と言いながら、カンフル剤の注射を強くしていくようなものですからね。要するに、刺激を過剰にしていく。僕はそれに違和感があって、大学院の頃にはポスト・モダン以前の磯田光一とか中村雄二郎とかを読んだし、右翼とも左翼ともつかない情念論みたいなものも好みました。

処方箋を焦る社会に対しては
急ぎつつ、待つ ―― 佐藤
先崎 さらに時代を下っていうとフランスの現代思想でいうような流動・移動をよしとする思想が、例えば実際にこの国で、震災を経験した人たちに、どれだけ説得力をもったのか。「思想の強度」が試されたと思ったのです。故郷を離れざるを得なかった人たちの心情を、流浪を肯定する思想でカバーすることが本当にできるのか、と。
佐藤 新刊の『違和感の正体』では震災、沖縄、教育など、身近な問題に迫ってますね。
先崎 はい、『ナショナリズムの復権』が哲学的思考の原理論とすれば、そういった理論の骨格を使いながら、時事的な問題について考えるヒントを提示したのがその本です。
佐藤 沖縄問題のところで、聞得大君(きこえおおきみ)が登場したのも面白いと思いました。この最高位の神女をはじめ、沖縄には独自の概念がいくつもあります。例えばマブイというのは魂のことで、沖縄の人間はマブイを6つくらい持って生まれてくる。でも痛いことやショックなことを経験すると落ちてしまうんです。
佐藤 うるま市で殺人事件がありましたよね。白骨の娘の遺体は帰ってきたけれど、全部のマブイが揃ってないから父親が探しているという記事が新聞に載る。この感覚が沖縄の保守性なんです。
先崎 死生観、霊魂観など、死者をどう扱うかという研究はナショナリズムを考える上で非常に重要だと思います。それを「死者の慰霊を国家権力によって回収され~」とすぐに思いつくような人は、柳田國男など民俗学的な資料を読んだことがないのでしょう。
佐藤 江藤淳にも影響を受けているとおっしゃっていましたね。
先崎 はい。彼の言葉で面白いのは、国家というのはやせ我慢だとしきりにいうことです。一例を挙げて説明すると、必死に働いて家に帰ってくると、反抗期の息子が突っかかってくるとする。その父親は外回りの仕事で、つまり外交なので頑張って帰って来たのかもしれないのに。国家というのはそんな父親のようなものだ、と。江藤淳は夏目漱石を例に出しているんですが、その感覚には深く納得させる部分があります。だから一部の人たちが、「国家は巨大な権力だ」として、覆すことを前提にものをしゃべるのって、江藤の論理からすると逆、または成熟していないということになる。

思想家たちの言葉を冷静な手つきで
いじることが現代には必要 ―― 先崎

佐藤 分かります。ただそれは余裕がないと難しい。
先崎 『違和感の正体』では思想家たちの言葉を"処方箋"として紹介しているのですが、佐藤さんは今の社会においてどんな処方箋が必要だとお考えですか。
佐藤 むしろ処方箋を焦る社会に対して「急ぎつつ、待つ」という言葉が浮かびました。プロテスタント神学者のカール・バルトのパクリなんですけど。私は、基本は待機主義なんです。状況が変わらない限りは。
先崎 なるほど! 福田和也門下の友人たちと、ロマン主義についての同人雑誌を出したときのテーマが、ズバリ「待機」でした。いずれにしてもナショナリズムという言葉は感情を高揚させることもあれば逆なでもする、人を興奮させる危険な概念なのは事実です。だからこそ思索して、ある論点までを導き出してくれた思想家たちの言葉を、冷静な手つきでいじることこそ、今のきな臭くなっている時代に必要だと。自分の著作は、安易にナショナリズムという言葉が出てきたとき、立ち止まり考えるきっかけを提供できればと、そんなふうにも思って書きました。
佐藤優 さとうまさる 作家 1960年生まれ 東京都出身。元外務省・主任分析官として情報活動に従事したインテリジェンスの第一人者。"知の怪物"と称されるほどの圧倒的な知識と、そこからうかがえる知性に共感する人が多数。近著に「『資本論』の核心 純粋な資本主義を考える」(角川新書)など。
先崎彰容 せんざきあきなか 倫理学者 1975年生まれ 東京都出身。東京大学文学部倫理学科卒。東北大学大学院文学研究科日本思想史博士課程を修了。2016年4月より日本大学危機管理学部の教授に就任。著書に「ナショナリズムの復権」(ちくま新書)、「違和感の正体」(新潮新書)など。
構成/藤崎美穂
撮影/伊東隆輔
撮影協力/PROPS NOW TOKYO