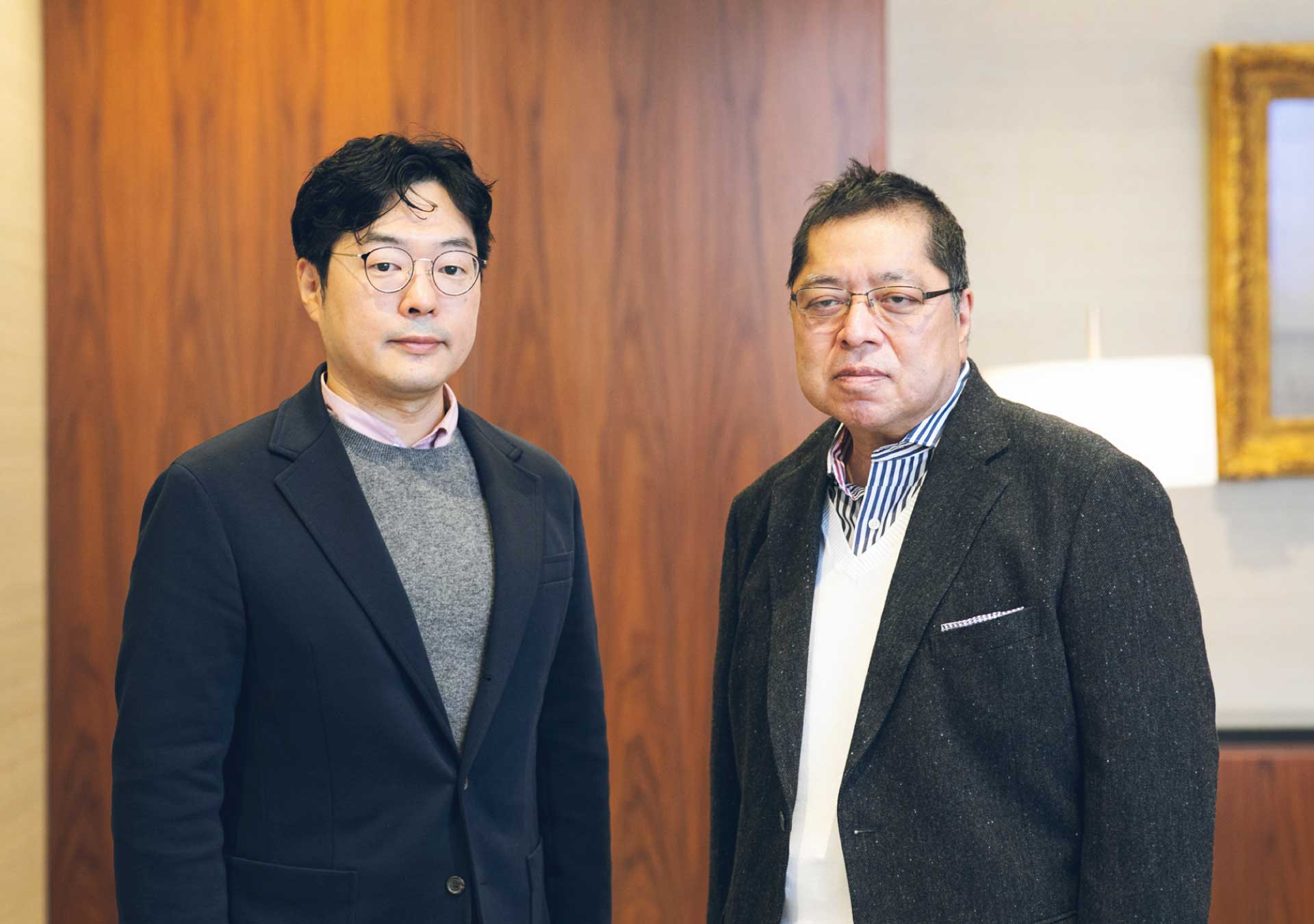今回は精神科医の松本俊彦さんが登場。
佐藤 松本先生は、薬物依存症や自傷行為の臨床、研究をご専門にされています。先日上梓された『身近な薬物のはなし』では、たばこ、カフェイン、アルコールをメインに、精神に影響を及ぼす薬物が人類の歴史や発展といかに密接に関わってきたかを紐解き、「薬物自体に良い悪いはなく、良い使い方と悪い使い方があるだけ」というメッセージを強く伝えられています。他のご本でも、当事者の苦痛や苦悩に寄り添われ、『「困った人」(依存症者)は「困っている人」だ』と、優しい視線で繰り返し述べられている。深く頷きながら読みました。
松本 ありがとうございます。私自身が当事者といいますか、依存体質の自覚があるんです。たばこもカフェインもアルコールもこよなく愛好しておりますし、強いストレスを感じたときには自傷行為に近いような激辛タンメンを食べてスッキリしていますから。覚せい剤を一度使ったらやめられなくなるタイプですね。

かえって悲劇的な方向に進むこともある。
佐藤 何にも依存せずに生きていられる人間なんていませんから。私も睡眠導入剤は手放せません。作家なんて言わないだけで、睡眠導入剤を常用している人は多いと思いますよ。毎日、本を読まずにはいられないし、一日に18時間くらい原稿を書き続ける日もざらにあります。たまたま社会的生産性があるから許されているだけで、依存行為の対象が違えばまた別の話になっちゃったわけですから。
松本 そうですよね。投資の世界で巨利を動かしているような方も、脳の働きとしては依存症に近い気がします。仕事自体がギャンブルになっているというか。
佐藤 ええ。官僚や政治家も似たようなものです。それに、宗教だって依存でしょう。毎週、教会に行ってお祈りを捧げて気持ちがすっきりする、というのも一種の依存行為です。まさにマルクスが『ヘーゲル法哲学批判』の序章で「宗教は大衆のアヘンである」と言ったように。

松本 そうですね。一時期、宗教2世問題が話題になりましたが、子どもに説得されて脱会した親が自分を支えていた信仰もコミュニティもすべてを失って、ひどい錯乱状態になってしまうケースに遭遇したことがあります。宗教に依存することで生きることができていたのかなと感じました。薬物依存でも「ダメ。ゼッタイ」と依存を断ち切ることが、かえって悲劇的な方向に進むこともこれまでの臨床経験からわかっています。むしろ私は、依存症に押し付けられたスティグマや、規制法によって社会的にスポイルされることのほうが有害ではないかと危惧しています。実際に近年の公衆衛生に関する研究では、たばこやアルコールよりも、孤独や孤立のほうがはるかに有害という論文がどんどん出てきています。
佐藤 それに、依存対象というのは移行しますよね。根本的な問題を解決しないかぎり。
松本 はい。アルコール依存症だった男性が断酒後にパチンコにハマったり、風俗通いがはじまったりというのは、以前からよくあるケースです。女性の場合はこれがさらに顕著で、アルコールや薬物を止めたとたん、摂食障害やリストカットが止まらなくなる方は多いです。
佐藤 そうすると、依存対象を排除するというよりも、依存せざるをえなくなった人たちの体験に寄り添い、社会で受け入れていくことがやはり重要になってくる。公的な支援を含めて。この社会では今後、依存症と呼ばれる人はさらに増えていくでしょうから。
松本 そうですね。プチ依存症のような裾野は広がっていくと思います。

常に良策とは思えない。
佐藤 臨床の現場では、今どのような症例が多いのですか?
松本 圧倒的に市販薬のオーバードーズです。特にカフェイン中毒による救急搬送数、死亡者数は2013年を期に急増しました。ちょうど、エナジードリンクが出回りはじめたのと同じ頃です。エナドリ自体はさほどカフェイン含有量は多くないのですが、コーヒーを飲まない若い世代が気軽に摂取できるようになってしまったのが、ターニングポイントだったのではないかと。今では中学受験の塾への差し入れがエナドリということもあるくらいですから。結果として、カフェインのハイになる効果に気づいた若い子たちが、さらに効率よくカフェインを摂取しようと、市販薬に目をつけたんです。風邪薬や鎮咳薬(咳止め)にはカフェインの他、精神に影響を及ぼすさまざまな成分が使われています。ほとんどが10、20代の女性なんですが、驚くほど成分に詳しいですよ。
佐藤 なるほど。カフェイン剤は私の学生時代からありました。高校生の文化祭準備か何かで3日くらい徹夜したときに飲んで、床から煙が出てくる幻が見えてびっくりしたのをよく覚えています。
松本 僕も学生時代には飲んでいました。でもカフェインは、疲れや眠気を感じるアデノシンという物質の受容体をブロックするだけですから、文字通り“元気の前借り”なんです。実際は疲労物質や眠気物質が溜まり続けているので、効果が切れたときにどっと借金を払わされる。朝のコーヒーがおいしいのも、要は睡眠中の断薬によって離脱症状が出ているからです。しかもアッパーになるような成分は、反動で抑うつや希死念慮を引き起こします。ここ数年で高校生女子の自殺数が急増していることも、無関係ではないと考えています。
佐藤 ざっくりした発言になってしまうけれども、グローバリゼーションや新自由主義が席巻したこの30年のしわ寄せが、構造的には相変わらずジェンダーバイアスがある中で、まだ人格が未形成な若い女性に向かっている。非常に良くない空気ですね。
松本 僕もそう思っています。ただし、依存が悪とは言えなくて、推し活といってホストに貢ぐために風俗で働いたり、トー横に集まったりする女の子たちって、保護されても釈放されるとすぐに戻ってしまうんです。そして、同じような境遇の子たちと現実のつらさを紛らわすために、市販薬を分け合っている。それは一種の自己治療なんですよ。世界的に見ても、薬物乱用に規制がかかると、自殺率が増える傾向があります。ある人はこのしんどい世の中で自殺を選び、ある人は依存で生き延びているんですよね。
佐藤 そうすると、先生のお考えでは、依存性物質あるいはスマホやゲームといった依存性を誘発する行為と、どういう付き合い方をしていくのが一番いいですか。
松本 メリットとデメリットを天秤に掛けて、メリットが大きいうちはいいと思うんです。例えば、最近は子どものゲーム依存の相談も多いんですが、楽しくやっているなら問題ない。学校に馴染めないけれどオンラインゲームの友達とは仲良くできる、という子もいます。そういう子からゲームを取りあげるのが常に良策とは僕は思いません。ただ、違法行為をしたり、誰かを害する行為があったり、本人がやめたいのにやめられない、他の生活面で犠牲が著しく大きくなっている場合は、専門機関での治療を検討したほうがいいと思います。
佐藤 病院に行くほど困ってはいないけれど、もう少し控えたいという人には、どのようなアドバイスをしますか。
松本 そうですね、お酒やコーヒーを飲みすぎてしまうのであれば、脱水症状を防ぐためにも水をたくさん飲んで中和を心がけるとか……あと問題行動の中には、丁寧に記録すると自然と減ることもあります。ゲームをした時間や、ソシャゲのガチャだったら何回まわして何回SSRが出たかというような勝ち負け記録をつける。過食衝動が出たときも、ちょっとだけがんばって立ち止まって、記録をつけられるといいと思います。
佐藤 レコーディング・ダイエットと同じですね。
松本 ええ。それでも良い方向にいかなかったり、やっぱりつらい気持ちになったりする中で、病院へ行くことに抵抗があったら、都道府県の政令指定都市にある精神保健福祉センターに予約をとって、1回話を聞いてもらったらいいと思います。お金もかからないですし、保険証も必要ありません。ギャンブルでもゲームでもアルコールでも薬物でも、違法薬物でも通報されることはありません。本人だけではなく、家族の方の相談にも乗ってもらえますから、一人で悩むよりは、ぜひ。
佐藤 保健所はよくやってくれますよね。ただ、先生のご本にも書かれていたけれど、治療というものに過度な期待はしないほうがいい。目標は完治ではなく、マイナスのミニマム化という発想で臨むことが大切です。反応を起こさないためにも。
松本 おっしゃるとおりです。僕は「やめない依存症専門医」と自称しているくらいです。いいんです、依存して。
佐藤 それから私が思うのは、「自分は依存症とは関係ない」と思う人ほど「自分自身が何に依存しているか」を自覚したほうがいいと思う。繰り返しになりますが、誰でも何かに依存しているのだから。そして、依存症は決して特殊な人の特殊な病気ではなく、たまたま自分の依存がそちらに行かなかっただけだ、という視点が今後の社会ではより必要になってくるでしょう。
松本 ええ。依存症に必要なものは、connection(つながり)です。先日、厚生労働省が公開した「OD(オーバードーズ)するよりSD(相談)しよう」という動画が炎上して取り下げられましたが、表現はともかく、相談を促すこと自体は悪くない。ただ、僕は「ODしていても相談しよう」と言いたいです。もっと言えば、相談じゃなくてもいい。何気ない雑談や、自分の困りごとについて話せる場所、安心できる場所として、治療や公的サービスを使ってほしい。そして、依存症への偏見を減らして、当事者を治療につなげやすくしていくことも、大きな課題だと感じています。


撮影/伊東隆輔
構成/藤崎美穂
スタイリング(佐藤)/森外玖水子
BACKNUMBER
- vol.1
- vol.2
- vol.3
- vol.4
- vol.5
- vol.6
- vol.7
- vol.8
- vol.9
- vol.10
- vol.11
- vol.12
- vol.13
- vol.14
- vol.15
- vol.16
- vol.17
- vol.18
- vol.19
- vol.20
- vol.21
- vol.22
- vol.23
- vol.24
- vol.25
- vol.26
- vol.27
- vol.28
- vol.29
- vol.30
- vol.31
- vol.32
- vol.33
- vol.34
- vol.35
- vol.36
- vol.37
- vol.38
- vol.39
- vol.40
- vol.41
- vol.42
- vol.43
- vol.44
- vol.45
- vol.46
- vol.47
- vol.48
- vol.49
- vol.50
- vol.51
- vol.52
- vol.53
- vol.54
- vol.55
- vol.56
- vol.57
- vol.58
- vol.59
- vol.60
- vol.61
- vol.62