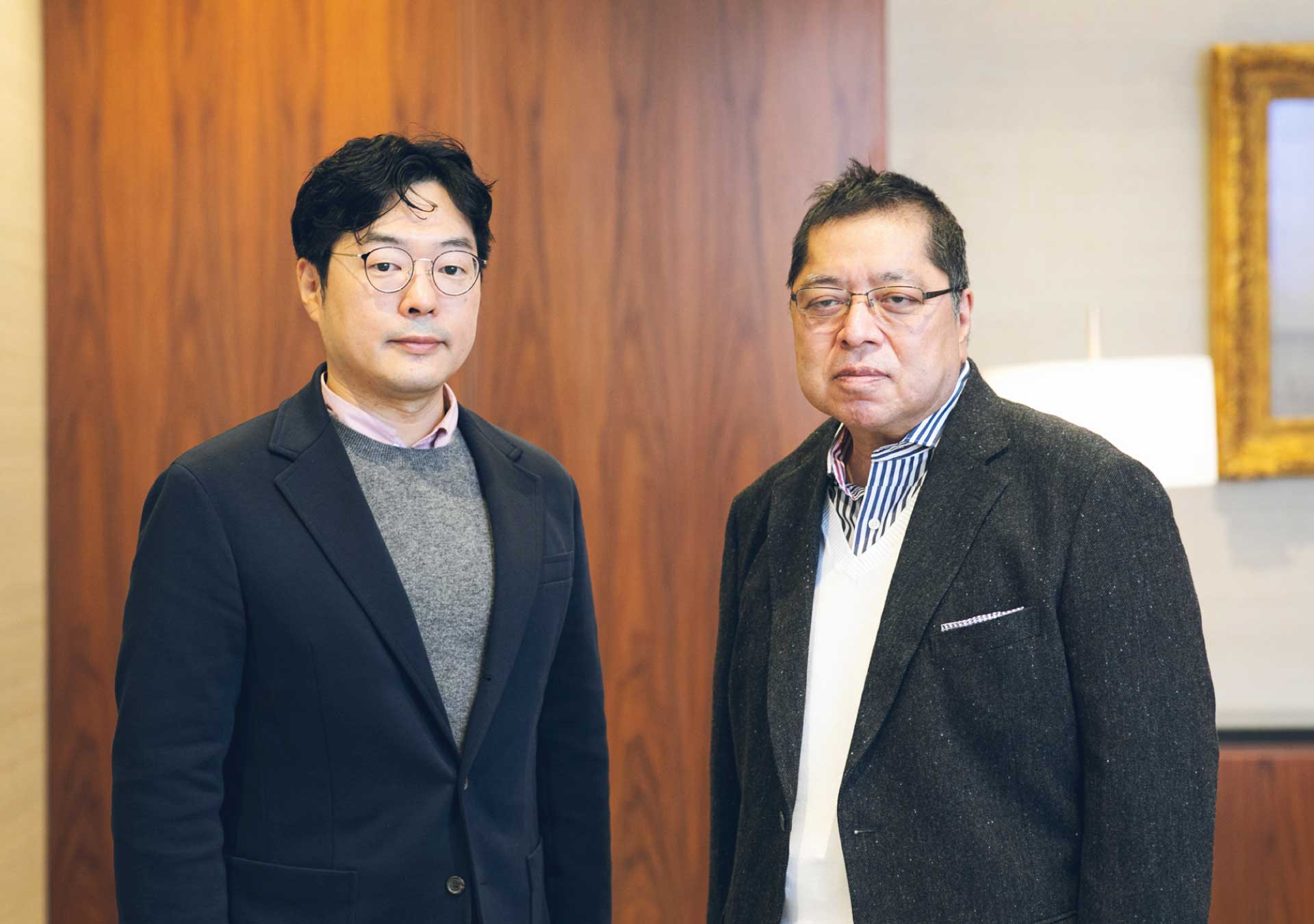今回はジャーナリストの古田大輔さんが登場。
佐藤 古田さんは朝日新聞、BuzzFeed Japan創刊編集長、Google News Labティーチングフェローなどを経て、2022年9月から、ファクトチェック(事実の検証)を専門とする非営利組織・日本ファクトチェックセンター(以下、JFC)の編集長をされています。
古田 はい。Googleにいたとき、日本のメディアの方向けにファクトチェックのセミナーを行っていたのですが、なかなか広がらず。ならば自分たちでやるしかないと、JFCを立ち上げました。活動の軸は大きく2つあります。1つはインターネット上の不確かな情報や、著名人の発言などの真偽を検証するファクトチェック活動。もう1つはメディアリテラシー教育の普及です。ネット上の不確かな情報は星の数ほどあり、僕らのチェックだけでは追いつきませんから。
佐藤 教育は大事です。具体的にはどのような活動を?
古田 この2年間で対面やオンラインのセミナーを約6,000人の方が受講されました。YouTubeでも無料の講座を公開しています。また学校の先生や企業の研修担当の方向けに講師養成講座も開講していて、修了された方には私達が使っている教材を提供し、各地でファクトチェックの裾野を広めてもらえる仕組みにしています。

簡単に騙されてしまう。
佐藤 日本では今までも、ファクトチェックにおけるfact(事実)とopinion(意見)を混同する人が少なくありません。そこから説明しないといけない。
古田 ええ。JFCがチェックするのはあくまでも客観的・科学的に判断可能なfactのみ。「雲が出ている。雨が降りそうだ。傘を持とう」という文章があったとして、検証するのは「雲が出ている」という部分だけです。雲が出ていれば「正」、出ていなければ「誤」。「雨が降りそう」「傘を持とう」といった個人の判断や行動、つまり思想・信条の自由、言論の自由などのopinionは害さないよう、我々自身にも厳しいルールを定めています。
佐藤 opinionまでチェックすると旧ソ連や現在の北朝鮮になりますから。
古田 問題は、そういった明らかに誤りである物事に対して、調べもせずに事実だと受け止めてしまう人が大量にいることなんです。昨年2万人を対象に調査を行ったのですが、実際に日本で拡散した15の偽・誤情報を見てもらい、見たことがある人に事実だと思うか質問したところ、51.5%の方が「事実だ」と回答しました。

佐藤 その数字はだいぶマシなほうでは? 見たものをそのまま事実と受け止める層は、感覚的にはもっと多いように思います。どこかに向かうとき、多くの人は深く考えることなく轍の上を歩いて行く。新たな道は踏まない。そうして道ができていくわけで。
古田 脳の特性としても、すべての人間にはバイアスがあって、自分の経験に基づいて受け入れやすい情報を事実と受け入れるようになっていますよね。そのことをまず知っておかないと。むしろ「自分は大丈夫」と思っている人ほど、簡単に騙されてしまいます。
佐藤 私が学生たちに説明するときは、ドイツの社会哲学者のユルゲン・ハーバーマスが『晩期資本主義における正統化の諸問題』の中で使った「順応の気構え」という言葉を引きます。岩波現代選書版の細谷貞雄さんの名訳だけれども。なぜ事実と違うことを人々が簡単に信じてしまうのか。すなわち、現在においては大量の情報がある。教育水準も高い。だから、1つ1つの情報を検証する能力はみんな持っている。ただし情報があまりに膨大な中での検証作業は疲れてしまうから、理解できないことがあったとき、誰かが自分を説得してくれることを受け身で待つようになる、と。半世紀以上前に指摘されていた傾向が、SNSの登場でさらに急激に加速している。

加害者になるリスクの両方がある。
古田 たしかに。通勤電車などでぼーっとスマホを見ているとき、流れてきた情報をいちいち検索して精査したくないですよね。でも事実かどうかわからない情報、特に意見が激しく対立するような情報に対しては、「いいね」や「シェア」ボタンを押す前に、一歩踏みとどまってほしいんです。それは偽・誤情報に騙された被害者になるリスクと同時に、偽・誤情報を拡散する加害者になるリスクもはらんだ行為ですから。
佐藤 今、若い官僚たちもファクトチェックに非常に関心を持っていますよ。
古田 そうですよね。ファクトチェックが世界的に大きな注目を集めたのは、2016年のアメリカ大統領選挙でした。僕らがファクトチェックをする記事の25%は政治関連です。一番多いのは、与党や政府、各省庁の発信に対する間違った情報に対しての検証です。政府や政党への批判はあって当然なのですが、ここ10年は、あからさまにアクセス数稼ぎを目的としたようなデマや誹謗中傷のようなものも増えました。
佐藤 アクセス数があれば金になるし、承認欲求も満たされますから。
古田 はい。また選挙関連でいうと、誤った情報を拡散する支持者の中には、自分の選択が正しいと信じたいという欲求を感じます。たとえば熱烈なトランプ支持者の中には「彼がやっていることにはすべて大いなる意図がある。彼が世界の民主主義を救うんだ」と主張する方々がいます。トランプさん本人が言ってないことまで事実とされ、勝手に神格化されていく。同じようなことを兵庫県知事選でも感じました。僕は斎藤元彦さんを応援するネット上のコミュニティーのいくつかを、かなり初期から見ていました。最初は「斎藤さんはいじめられていて大変だから応援しよう」と支援者が増えていった。それがある時点から「斎藤さんはとにかく素晴らしい知事だ」というストーリーに変化していったんです。
佐藤 宗教の論理ですね。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教。最近は創価学会がそうですけれども、これほどの世界宗教は正典(キャノン)に書かれた内容で、過去、現在、未来、森羅万象のあらゆることが説明できるとされています。アナロジーとメタファーの方法を用いることで。私が神学部で受けたのは、その訓練ですよ。森羅万象は新約聖書と旧約聖書で全部説明できる。できないのはhermeneutik(解釈学)の力量が不足しているからだと。トランプ大統領も斎藤知事も、無意識のうちに神学の手法を使っている。
古田 人は誰でも自分がかわいいし、自分が親しみやすい情報や、好意を持った相手を良く思いたい。だから、そういう信者のようになってしまった人にとっては、ファクトチェックは「敵」になっちゃうんです。ネット上で真実を見つけた私たちに対して、establishment側――旧来の既得権益層が攻撃をしてくる、と。そういった反応は、世界中で起こっています。
佐藤 establishment側というのはある意味、間違っていないんですよ。ファクトチェックは反知性主義との戦いでもある。
古田 特に「ナラティブ」にどう対応するべきかという話題は、世界のファクトチェッカーの間で議論が続けられています。単なるストーリー=物語ではなく、物語の語り手がどのような語り口で語っているか、この語り口をナラティブといいます。事実を織り交ぜながら、怪しげな語り口のナラティブが広がると、ファクトチェックをしにくい。
佐藤 なるほど、難しい問題です。ロシアも意外と嘘はつかない。稚拙な偽情報は流さない。けれど、いつの間にかストーリーが変化していく。だから怖い。手口を知らないと、強く反発していた人ほど簡単に騙されてしまいます。
古田 対抗してファクトチェッカーもナラティブを活用すべきだという意見もあります。僕は「すべきではない」という立場なんですが。
佐藤 それは、すべきではないと思う。ナラティブ対ナラティブの戦いは神々の争いになるから。事実ベースで来る相手には「語っていないfact」を提示していくのが一番いいと思います。
古田 そうですよね。だから僕は今、データベース化を非常に重要視しています。JFCのデータは、常に検索エンジンで上位に出るようにSEOの工夫をしています。偽・誤情報はソーシャルメディアで拡散しがちですが、Google検索でX上の投稿が一番上に出ることはほぼありません。だから、仮にXやYouTubeやTikTokの情報で偽・誤情報に興味を持ったとしても、立ち止まって検索してもらえたら、そこで騙されるのを食い止めることができる。ファクトチェックって、カルト信者のように盲目的になった方には届きにくいのですが、そこまでではない「なんとなくそうなのかな」と思っているような層には結構届くことが調査でもわかっているので。
佐藤 「順応の気構え」層ですね。
古田 はい。そういう穴に落ちかけた人が深みにはまる、その手前で食い止めるための作業も、我々の活動の主軸の1つです。
佐藤 なるほど。非常に重要な作業ですね。自然発生的な噂話は、尾ひれがついて広がっていくものです。けれど、ネット上で拡散する情報はそうではないケースが多い。つまり、金目的であれ、政治目的であれ、意図的な1つのストーリーに収斂(しゅうれん)していく大量の情報は、誰かが何かしら手を加えている。つまり、情報を裏でメンテナンスしている集団なり人なりがいるわけです。彼らは情報操作をして、民主的な社会の世論形成を壊していく。そういった情報をあぶり出すという意味でも、JFCの活動は非常に重要だと思います。
古田 これも先の2万人調査でわかったことなのですが、偽・誤情報を信じて拡散してしまった人に「なぜ拡散したのですか?」と選択項目式で質問したところ、一番多かった回答が「興味深いと思ったから」。次が「重要だと思ったから」。3番目が「その情報に怒りや不安を感じて自分の感情を表現したかったから」でした。誰も悪いと思ってやっていない。むしろ良かれと思っての行動ですし、3番目は完全に正義感の暴走です。そういった調査結果を含め、ファクトチェックの方法、正しい情報にアクセスするための検索の仕方などもJFCのサイトですべて無料で公開しています。「JFCファクトチェック講座」はテーマごとに5分~10分ほどのYouTube動画で計20本、誰でも視聴可能ですから、読者の皆さんもぜひ、観てみてください。


撮影/伊東隆輔
構成/藤崎美穂
スタイリング(佐藤)/森外玖水子
BACKNUMBER
- vol.1
- vol.2
- vol.3
- vol.4
- vol.5
- vol.6
- vol.7
- vol.8
- vol.9
- vol.10
- vol.11
- vol.12
- vol.13
- vol.14
- vol.15
- vol.16
- vol.17
- vol.18
- vol.19
- vol.20
- vol.21
- vol.22
- vol.23
- vol.24
- vol.25
- vol.26
- vol.27
- vol.28
- vol.29
- vol.30
- vol.31
- vol.32
- vol.33
- vol.34
- vol.35
- vol.36
- vol.37
- vol.38
- vol.39
- vol.40
- vol.41
- vol.42
- vol.43
- vol.44
- vol.45
- vol.46
- vol.47
- vol.48
- vol.49
- vol.50
- vol.51
- vol.52
- vol.53
- vol.54
- vol.55
- vol.56
- vol.57
- vol.58
- vol.59
- vol.60
- vol.61
- vol.62