


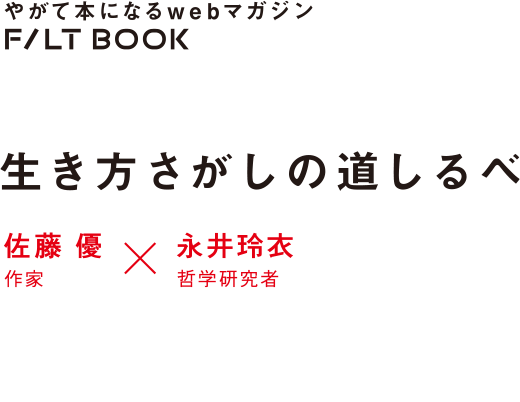

撮影/伊東隆輔
構成/藤崎美穂
スタイリング(佐藤)/森外玖水子
『問う』ことで自由になろう
絶対に必要だという気持ちで、
哲学対話を続けている ―― 永井
佐藤 永井さんは哲学者、さらに実践家として、学校や企業、自治体など様々な場所で哲学対話のファシリテーターをされています。いま哲学カフェはどのくらい運営しているんですか?
永井 月に一度、10年ほど定期的に続けている会が一つあって、それ以外は月に何度か、都度依頼を受けて行うかたちです。
佐藤 哲学をテーマにしたサロンにはカルト化するリスクが伴います。『ゼロからはじめる哲学対話』(ひつじ書房)に寄稿された原稿では、いかにそのリスクを排除するかについて細かく書かれているのが印象的でした。例えば、ふつう組織を立ち上げるときには終わりを考えないんだけど、必ず終わる組織であることを前提にしている。差別的な発言や攻撃的な発言をする人が出てきたときはどう対応するか、というような問題点にも非常に丁寧に言及されています。
永井 哲学対話というと素朴にポジティブなイメージを持たれがちですが、対話やコミュニケーションは難しいものだというところがスタートなんです。私自身10代の頃から今もずっともがいていて、人の脆さや加害性――カルト化もそうですし、常連になった年配の男性が威張るとか、そういうことに直面しながら奮闘しています。
佐藤 年配男性が威張る問題はリカレント教育でも起こりがちです。会社でパッとしないまま定年退職した人が社会人入試で大学院に来て、「俺は若い頃に亀に乗って龍宮城へ行ったんだ」なんて武勇伝を語りだすと、若い人たちに大変な悪影響を与える。なかなか大変な場作りだと思うのですが、面白いですか?
永井 うーん…そうですね……哲学対話って、参加される方が大体二つのタイプに分かれるんです。割合として「考えるのが好き!」というポジティブな方が多いんですけど、一方「辛いけど考えざるをえない……」という感じの方もいて、私は後者です。人と話すのは苦しいですし、引きこもり体質なのであまり表にも出たくない。でも絶対にこれが必要でやらなきゃいけないんだ、という気持ちでやっています。
佐藤 私も社交的に見られることがあるけど、それは仕事だから。本当は一人で本を読んでるか猫と話してるほうが好きですね。それにしても永井さんの研究のご専門がサルトルと聞いて少し驚きました。私が学生のときでもサルトルに興味を持っていると「古いものを読んでいるね」と言われたけれど。
永井 大学でも驚かれました(笑)。10代の頃、あまりにも世界や他者というものがわからなくて、答えを探すように文学を読んでいたんです。そして好きだったカミュやカフカからサルトルに行き着きました。『実存主義とはヒューマニズムである』に書かれていた「とにかくおまえが考えろ」「おまえがつくれ、自分を」といった内容に、すごく衝撃を受けて、同時に、これからは一生サルトルと考えて生きていけばいいんだ、と決意して哲学科に進学して、今に至ります。
佐藤 カミュやカフカも、私より10歳くらい上の世代、今70代くらいの方が熱中して読んだイメージです。どういう出会いがあったんですか。
永井 図書館で左端から順番に読んでいきました(笑)。
佐藤 まさにサルトルの『嘔吐』に登場する「独学者」の読み方ですね。アルファベットのAから読んでいく。
中高の環境は学ぶことが
良しとされず苦しかった ―― 永井
永井 でも中高の環境は学ぶことや本を読むことがあまり良しとされていなくて、すごく苦しかったんです。何か疑問に思っても「そんなことを考えてどうするの」「変なの」と言われてしまって。
佐藤 高偏差値校の一角にありがちな光景です。真面目に勉強するのはかっこ悪いというイメージがあるから、隠れてするんだよね。
永井 それが上智大学の哲学科に入って一変しました。研究室では年齢関係なく誰もが問いに対してオープンに対話してくれます。問うことは何もおかしくない、という場に初めて触れて、とても自由になれて。私もこういう場所をたくさん作りたいと思ったのが、哲学対話を始めた原体験になっています。

哲学的な思考の形は
周期的に戻ってくる ―― 佐藤
佐藤 人と話すのが苦手とおっしゃるけど、書かれたものを読んでいると優しい人柄が出ています。自分が苦しかったからこそ、ほかの人にも哲学を通じて一つの糸口が見つかることを伝えたい……という思いが、行間から伝わってくる。
永井 ありがとうございます。でも当初はかなり戦闘的な他者論をやっていました。とにかく苦しくて糸口すら見つからなくて……サルトル初期の、生身の人間への嫌悪みたいなものが強く出ている作品に惹かれたんですよね。でも中期の『倫理学ノート』――これはノートに書かれたメモの断片を集めた遺稿なんですが、その中には、生身の人間となんとかもがいて話そうとする、とにかく呼びかけるんだ、という意思が出てきます。哲学対話もいまやっているD2021も、自分の活動の全てはサルトルのアンガジュマン(社会参加)の概念に影響を受けています。
佐藤 サルトルの提唱した実存主義は、その後の構造主義、さらにポスト構造主義の台頭によって過去の遺物のように扱われました。しかしこういった風潮は間違っています。哲学的な思考の形は周期的に戻ってくるものでもあります。実際にいま、実存主義は再び注目されてきていますからね。
永井 おっしゃるとおり、サルトルは構造主義にもポスト構造主義にもボコボコに叩かれて、共産党からもカトリックからも右派からも嫌われて……。最初は反論したい気持ちになりましたけど、だんだん、批判があるってありがたいと思うようにもなりました。反対意見があるから、弁証法的に物事が進んでいくこともある。哲学対話も同じで、批判が重ねられて緊張関係があって、だからこそテーマが掘り下げられていく場であってほしいと思っています。「何を話してもいいし、話さなくてもいい。正解はありません」というとたまに勘違いされるんですが、みんなが安心して話せてみんなで分かち合って……というような、対立のない場が理想なわけではないんです。
佐藤 それじゃ新興宗教か自己啓発セミナーの座談会だ(笑)。

自分の欲望に気づくことが
自由へのきっかけになる ―― 永井

永井 (笑)。ただ批判を非難だと思い込んでいる方も少なくないので、その場合は認識から解(ほど)いていく必要がありますが。意見や主張ってだいたい別の欲求が隠れています。例えば何か対立があった時、なぜそう思うのか、そもそも何が問題なのかと掘り下げていくことで、本当に求めていることに辿りつくことが多いんです。様々な意見の対立や葛藤を解すという意味でも哲学対話は貢献できるんじゃないかなと。
佐藤 コロナ禍での変化はありますか。
永井 やはり集まりにくい状況なので、オンライン開催をするようになりました。「場」としては直接顔を合わせるほうが望ましいと思っていたんですが、オンラインならではの問題も出てきて、新しい工夫が必要で。それはそれで、良い刺激だと思っています。
佐藤 全てを考えるきっかけと捉えるわけですね。
永井 それとこれは人数が多くてカフェ形式で対話ができないときに、一人ひとりに用紙をお配りしてやったワークなんですけど。問題に思っていることを書いて、その下にどんどん「なぜそう思うのか」を書き連ねていくんです。そうすると、本当に問いたい内容が浮かび上がってきます。ひとりで苦しい時には、そういうワークも役立つかもしれません。
佐藤 哲学カフェのようなことを一人でもできる。
永井 そうですね。深めていくには他者が必要だとは思いますが、まず自分の中に隠れている欲望に気づくだけでも違うのではないかと。「それはなぜ?」「そもそも本当に?」と問うことが、誰かが決めた常識に縛られていることへの気づきや、自由になるきっかけになったらいいなと思います。
佐藤 優 さとうまさる 作家。1960年生まれ、東京都出身。元外務省・主任分析官として情報活動に従事したインテリジェンスの第一人者。“知の怪物”と称されるほどの圧倒的な知識と、そこからうかがえる知性に共感する人が多数。第48回菊池寛賞受賞。近著に『本は3冊同時に読みなさい』など。
永井玲衣 ながいれい 哲学研究者。1991年生まれ、東京都出身。立教大学兼任講師。専門は哲学、倫理学。さまざまな場所で哲学対話を実践。雑誌『ニューQ』のほか、Webメディア『HAIR CATALOG.JP』で「水中の哲学者たち」、『晶文社スクラップブック』で「手のひらサイズの哲学」を連載中。
撮影/伊東隆輔
構成/藤崎美穂
スタイリング(佐藤)/森外玖水子