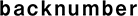第7回「シェアする暮らし」
2015.12.20

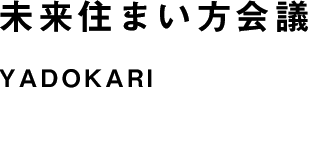
アートディレクターのさわだいっせいとプランナーのウエスギセイタを中心とする「住」の視点から新たな豊かさを定義し発信する集団。ミニマルライフ、多拠点居住、スモールハウスを通じ、暮らし方の選択肢を提案。主な活動は、『未来住まい方会議』運営、スモールハウスのプロデュース、空き家・空き地の再利用支援ほか。
250万円のスモールハウス『INSPIRATION』販売開始。http://yadokari.net/
2015.12.20
一人暮らしに憧れていた。湯船にのんびりとつかっていても、3食きちんと採らなくても、一日中布団の中でごろごろとしていても、誰にもなんにも文句を言われない暮らし。だから都内の大学に合格して一人暮らしを始めた時、「なんて自由!」と感動したのだ。好きなテレビ番組は見放題、毎日食べたいものだけ食べればいいし、眠くなったらその場で寝てしまえばいい。20平米というワンルームマンションの狭さはたいして気にならなかった。ひとつ不満があるとすれば、作り付けのガスコンロが一口しか無いことくらい。
交通の便も良いそのマンションに、大学を卒業して就職してからも住み続けていた。しかし社会人になってみると、学生時代は頻繁に遊びに来ていた友人たちにも、そうそう会えなくなった。残業から帰って、ばったりと倒れるように眠る。そういえばここのところ、職場と部屋とを往復する日々の繰り返し。仕事関係以外で人と話したのは、何ヶ月前のことだったろう?
隣の部屋には男子学生が住んでいるようだ。毎晩友人たちが押しかけて来て騒がしい。自分も少し前まではそうだったくせに、急に羨ましさと腹立たしさと、心細さを感じてしまう。隣がうるさければうるさいほど孤独にさいなまれる。結婚すればいいのか? いや、血の繋がった両親とさえ一緒に暮らすのが面倒だったから一人暮らしを始めたというのに、まったく違う環境で育った人間同士が一つ屋根の下で暮らせるものだろうか。
「ホームパーティーをするから、いらっしゃいませんか?」
そう誘ってくれたのは、仕事で知り合ったフランス文学専攻の若い研究者だった。
「オニオングラタンスープの作り方を覚えたので、ぜひ皆さんに披露したいんです」
同僚たちと押しかけた郊外の彼の家は、30代の独身男性が住んでいるとは思えないくらい、古びてはいるけれど広々としたアパートだった。
「ここに一人で住んでいるんですか?」
「いいえ、フランス人の留学生とシェアしています」
非常勤講師の収入ではこんな広い部屋は借りられないし、お互いの語学の勉強にもちょうどよかったので、と、ずり落ちた眼鏡を直しながら控えめに笑った。もともと知り合いだったわけではなく、人づてに住む場所を探している留学生を紹介してもらったのだと言う。家賃と光熱費とを合わせて、彼が計算して取りまとめているのだそうだ。すごい、よくわからないけど、さすがフランス。熱いオニオングラタンスープをすすりながら、やたら感心した。あれは2008年のこと。まだ「シェアハウス」なんていう言葉は耳にしなかったし、日本でもそんな暮らし方が広まるなんて思わなかった。
その後、シェアハウスという暮らし方が日本でも広まり始めていると知ったきっかけは、たまたま書店で手にした『東京シェア生活』(ひつじ不動産監修、アスペクト、2010)だった。自分たちで家賃を按分して普通の賃貸を借りるのが、他人と住まいをシェアする唯一の方法だと思っていたけれど、知らない者同士が一つ屋根の下で円滑に生活できるよう、事業体が仲介するタイプの物件もあるのだと知った。
好きなドラマがある。木皿泉が脚本を書いた『すいか』。2003年の夏に日本テレビの土曜ドラマ枠で放映されていた。「ハピネス三茶」という古いアパートが物語の舞台である。朝晩の2食付きで、居住者が食堂に集う賃貸。2003年当時、シェアハウスという言葉は聞かなかったが、この古いアパートはまさにそれだったろうと思う。27歳の売れない漫画家、女学生の頃から39年間住み続けている大学教授、オーナーの娘で皆の食事を作る大家の女子大生、そして、遅い親離れをするべく越してきた34歳の主人公。年齢も職業も、育ってきた環境も違う面々が同じ場所に住み、食卓を囲う。平凡だけれど毎日が違う日々。どんな日であれ、誰かと並んでご飯を食べられる。それはともすれば、暗がりでコンビニ弁当をがっついて済ませがちな日々を送っていた自分には、羨ましすぎる日常だった。
一人暮らしは気ままで自由。でも、多少不自由であったとしても、誰かがすぐそこにいる生活は心強い。かつてそれは、血の繋がった家族同士か、結婚でしか手に入らないものだと思っていたけれど、どうやらそうじゃないみたいだ。広い物件に安く住めることだけがシェアハウスの利点ではない。事業体が仲介するタイプのシェアハウスは、一人暮らしとそんなに変わらない家賃のところも多い。それでもシェアハウスの需要は伸び続けている。人々は新しい時代の「村」を求めているのかもしれない。
これまでの「村」という仕組みは窮屈だった。生まれた場所に縛られ、しがらみを感じる共同体。そういうものから逃れるように、都会ではそれぞれが壁に囲われた個室に住み、隣の人の顔さえ知らないという暮らし方が一般的になった。切り離された自由さは、しかし時が経つと不安に変わる。自分の「村」を、自分の属する共同体を自分で選び、ゆるやかに繋がって生きていく。居場所を所有するのでなく、シェアする。それは、物を持つことよりも、みんなで分け合うことの方が豊かだと感じるようになった世代にとって、とても自然な生き方なのかもしれない。