撮影/野呂美帆
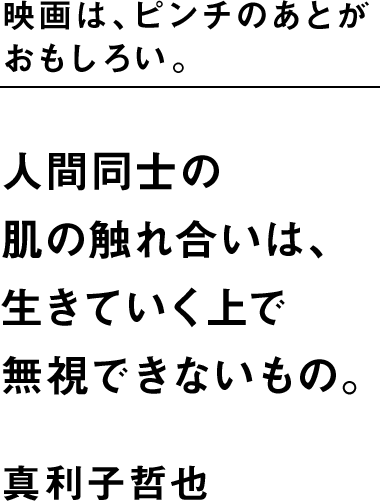
撮影/野呂美帆
2019年3月末に文化庁の新進芸術家海外研修制度によって渡米した真利子監督は、2020年3月半ばに帰国。すぐに緊急事態宣言が発出され、自宅待機を余儀なくされた。
「『宮本から君へ』の初号試写が終わった後、すぐに渡米しました。日本にも度々帰って来てはいたんですけど、基本的には1年ほど滞在していまして、いよいよ本帰国したらこの状況で。アメリカにいた頃から日本とはリモートでやり取りしていたので、それが続いている感じです」
真利子監督はアメリカで撮影する短編映画の企画を進めていたが、新型コロナウイルスの影響で一時中断。帰国してからは、また別の企画を進めている。

「完全リモートでの企画をいただいたので、世界中の友人や知人にビデオレターのような形で、コロナ渦の食卓を撮影してもらうことにしました。どんな形で完成できるのかは、まだわからないんですけど、世界中が外出禁止という状況の中での日常が集まっているので、面白い作品になりそうです」
『宮本から君へ』も、人との縁が繋いだ作品だった。
「どんな映画でも人との繋がりがあってはじまって、そこに集まった人たちのこだわりがぶつかり合って、匂い立つものなので、そのきっかけとなるご縁はこれからも大事にしたいですね」
今後、真利子監督がどんな映画を作っていくのかも気になるところ。
「日本映画がこれまでずっと抱えていた課題と向き合うべき局面にいるからこそ、今までのやり方だけじゃなくて、新しいことにも挑戦できる状態でありたいと思っているんです。監督としてアニメーションにも携わってみたいし、これまでにない発想で映画を作ってみたい。オリジナルでやりたい題材もあるんです。たとえメディアが変わっても映画の魅力を持ち続けて、いつかは撮りたいという思いがあります」
世界中に広がったコロナ禍の波は、映画の作り方を変えていく。しかし、そこから気づくこともあった。

「日常生活を撮影してもらう企画の中で、ある俳優夫婦から“肌の触れ合いを見せてはどうか”という提案があったんです。今まで当たり前だった密な交流が敬遠されているからこそ、より他者と触れ合うことの重要さに気が付かされました。人間同士の肌の触れ合いや、ぶつかり合いみたいなものって、感情の現れであって、生きていく上でどうしたって無視できないものだから、これからも人間を描く上では常に意識していたい。『宮本から君へ』の撮影を思い出しても、すぐにああいうものを作れる状況ではないですけど、それでも、どうやって新しい時代でも観る人の感情に触れる映画を作るのかは、映画監督として考えていかなきゃいけないことではあると思います」
真利子哲也 まりこてつや 映画監督。1981年生まれ、東京都出身。東京藝術大学大学院映像研究科の修了作品『イエローキッド』(2009年)で長編映画監督デビュー。『ディストラクション・ベイビーズ』(2016年)が、第69回ロカルノ国際映画祭最優秀新進監督賞の他、多数の映画賞を受賞。2018年放送のドラマ『宮本から君へ』では全話の脚本・演出を手掛け、2019年に映画化。同作は、第62回ブルーリボン賞監督賞や第32回日刊スポーツ映画大賞主演男優賞、監督賞などに輝く。
撮影/野呂美帆