

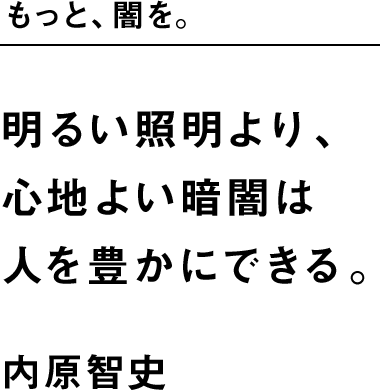
撮影/Jan Buus
取材・文/石原たきび
取材協力/虎ノ門ヒルズ、
NHK放送博物館
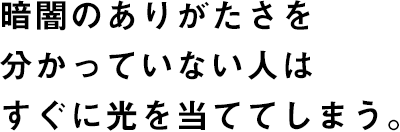
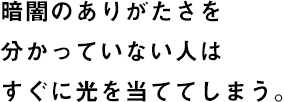
2014年に開業した52階建ての超高層ビル、虎ノ門ヒルズ。手がけたのはライティングデザイナーの内原智史さん。最上部には、内原さんのデザインした、このビルを象徴する光が瞬いている。一方で、レストランフロアは極限まで明るさを抑えた仕様デザインになっているという。
「コンセプトは、『コンフォータブル・ダークネス』、つまり『快適な暗さ』。ぎりぎりまで暗さを追求した照明デザインです。ほどよい明るさの抑揚で食事や会話に集中できるし、プライバシーも守られる。大事なのは食べながら会話するという行為の中に創造性のキャパシティがあるかどうか。全部見えちゃうと、それがなくなってしまう」
内原さんの事務所では、過去22年間で約760ものプロジェクトを担当してきた。その中の一つに金閣寺のライトアップがある。この時に衝撃的な体験をしたと彼は言う。

「照明のセッティングは夜中の作業。真っ暗闇の中、胴長を履いて池にじゃぶじゃぶ入ったんですが、パッと目を上げると見えるような見えないような茫洋とした感じで金閣寺が厳然と建っている。もう鳥肌が立つぐらい美しい。これに光を当てるなんて嫌な仕事だなあって、心の底から思いました(笑)」
実際に平等院鳳凰堂をライトアップした際は、建物そのものではなく、その前の池に光を当てた。「水の揺らぎを通して建物が浮かび上がり、悠久の時の流れが表現された」ということだ。
「照明の世界でも、暗闇のありがたさを分かっていない人はすぐに光を当ててしまう」と内原さんは嘆く。
視覚は情報の塊だ。光をどんどん暗くしていくと、想像力で補うしかない。暗闇が怖いのは、お化けという想像の産物が爆発しそうになるから。想像力が豊かな人ほど暗闇を怖がる。つまり怖がりは才能なのだと内原さんは言う。
「日本の狭い居住空間の中で夫婦喧嘩が絶えなかったら、照明を暗くすればいい。奥さんが料理を作るキッチンの周辺だけを照らす光。会社から帰った旦那さんがくつろぐリビングのソファーだけを照らす光。そして、双方の間に心地よい暗闇を作るんです」
LDKの真ん中で煌々とした光る蛍光灯が照らすのはボクシングのリング。一つの光の中で人間の生理が闘争本能を掻き立てられる。一方で、間に闇を設けた場合、キッチンの隅のゴミやよれよれのスーツなどの余計なものが見えない。お互いのテリトリーが別々の光で守られ、2人は余計なことに干渉しなくてすむ。さらに、情報を想像力で補いながら、“思いやりの会話”が始まる。室内の照明を暗くすると夫婦円満、結果的に少子化対策にもなる。そう言って内原さんは笑う。

例えば、東京のランドスケープの中心には皇居がある。24時間都市といわれる東京において、夜光らないあの闇こそが東京の夜景のアイデンティティだという。皇居をライトアップしたがっている人は数多くいるそうだが、内原さんはそれに異を唱える。
「我々はこれまでに、闇を煮たり焼いたり揚げたり刻んだり、いろんな調理をさんざんしてきました。表現しようとしているものは言葉ではなく、言葉が表している空間や雰囲気。それを伝えるためには、相手がその言葉から感じる想像領域をどれだけ広げてくれるかが重要なんです。光と闇の間の幅をうまく使えば、非常に豊かなコミュニケーションにつながると思います」
ゲーテは「もっと、光を」と言った。内原さんは「もっと、闇を」と主張し続ける。
内原智史 うちはらさとし 1958年生まれ。京都府出身。多摩美術大学卒業。ライティングデザイナーとして、これまで、東京国際空港国際線旅客ターミナル、虎ノ門ヒルズ、六本木ヒルズのクリスマスイルミネーションや京都金閣寺、銀閣寺、平等院鳳凰堂などのライティングデザインを手がけてきた。
撮影/Jan Buus 取材・文/石原たきび
取材協力/虎ノ門ヒルズ、NHK放送博物館
ヘアメイク/河嶋 希
スタイリング/佐山みき